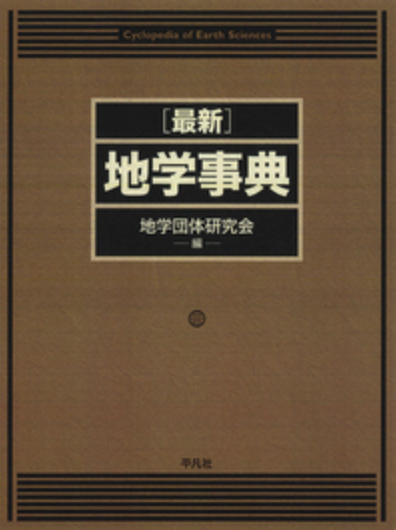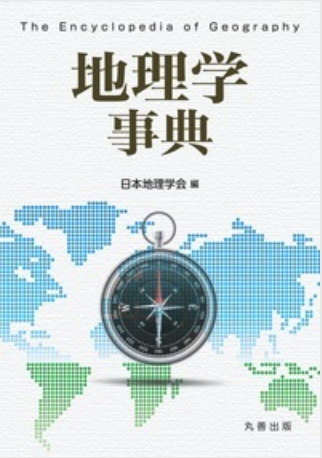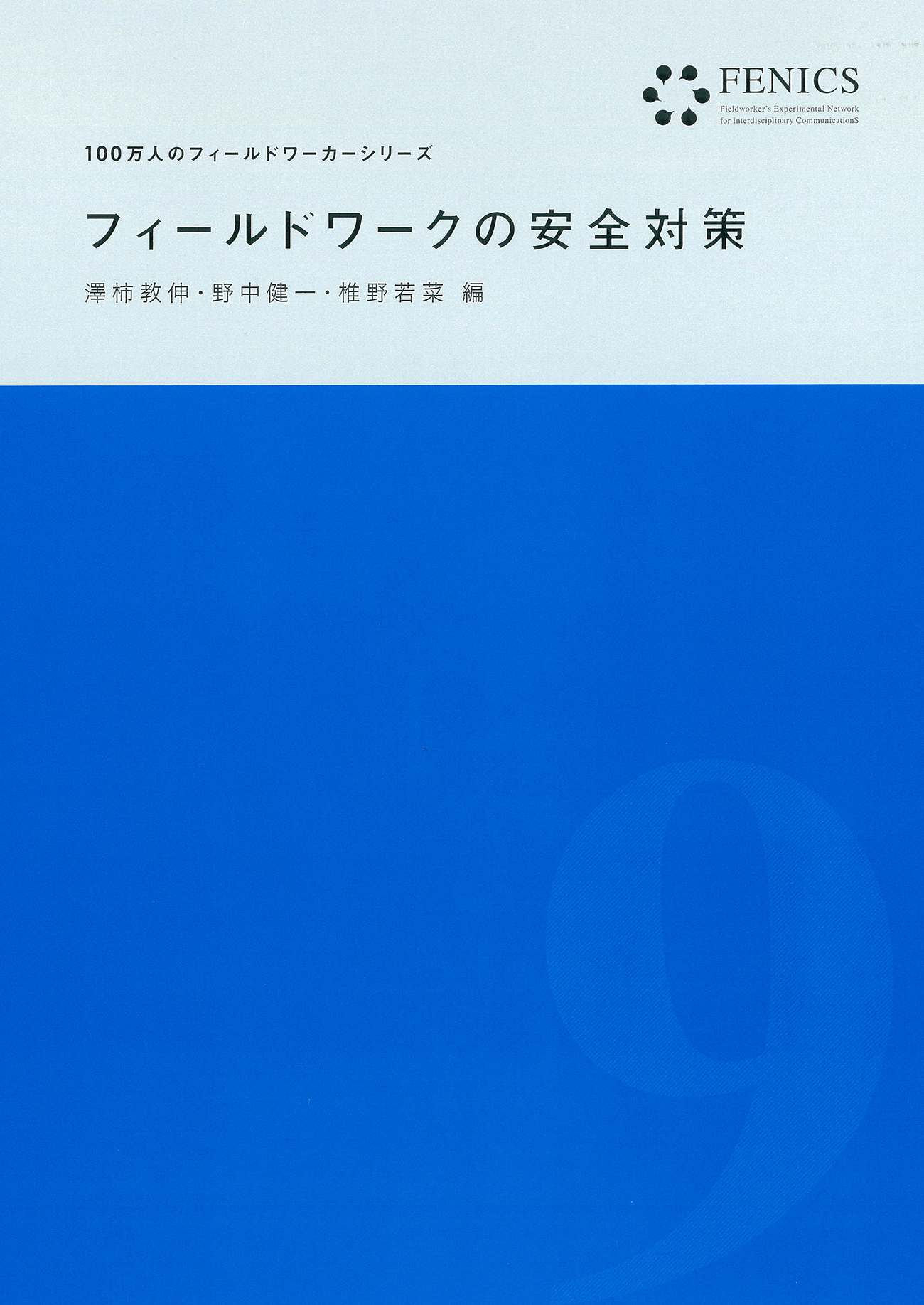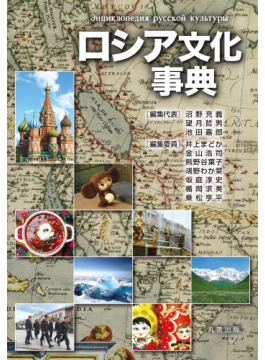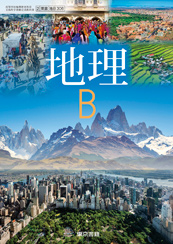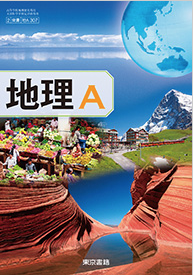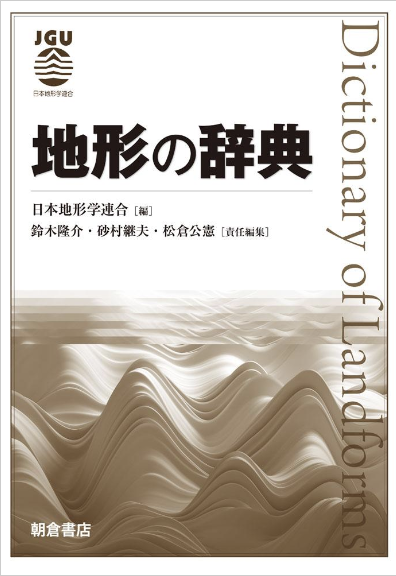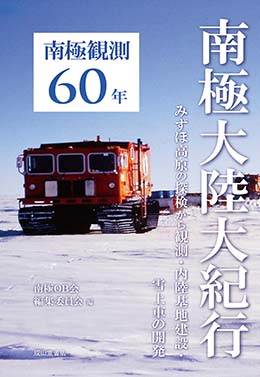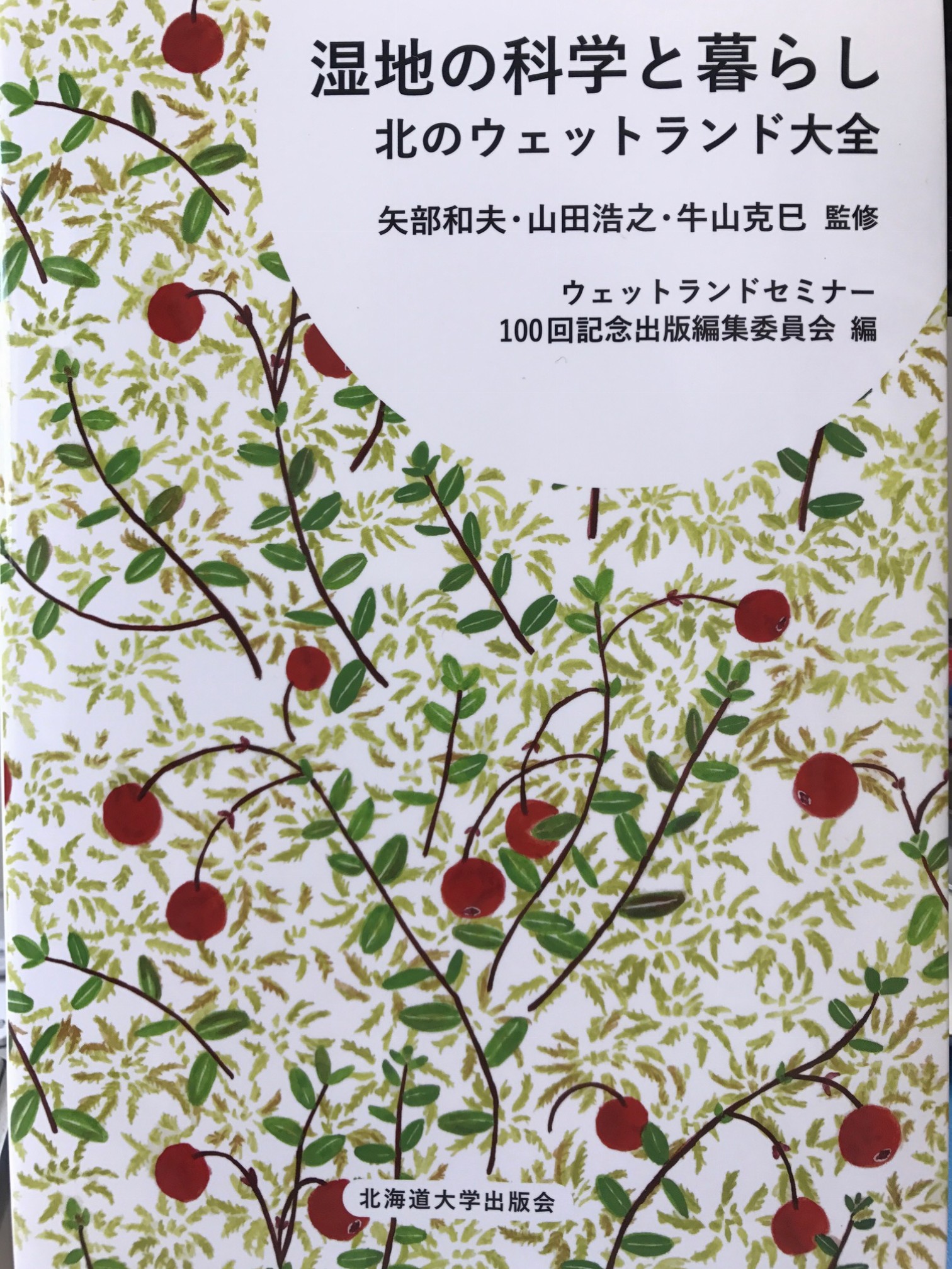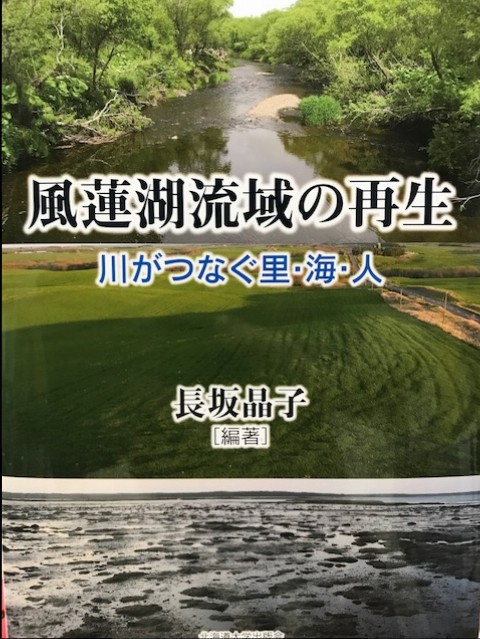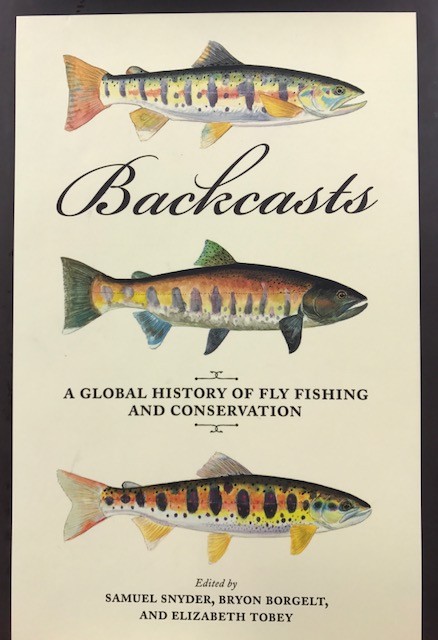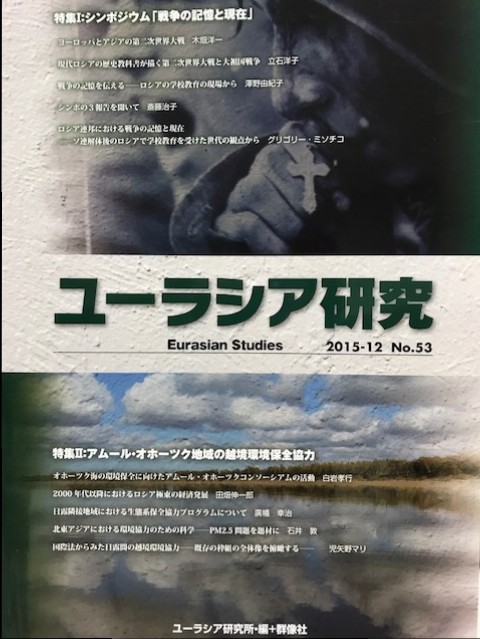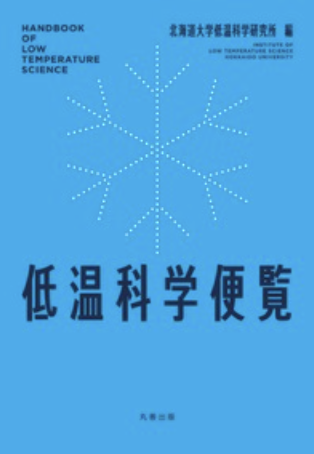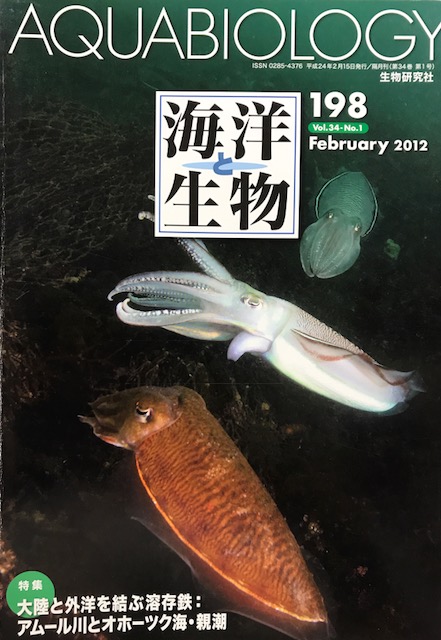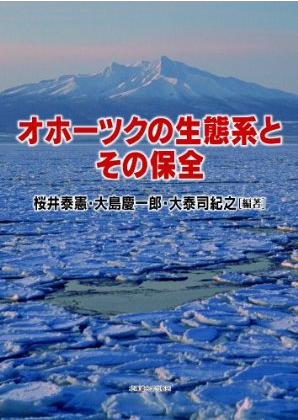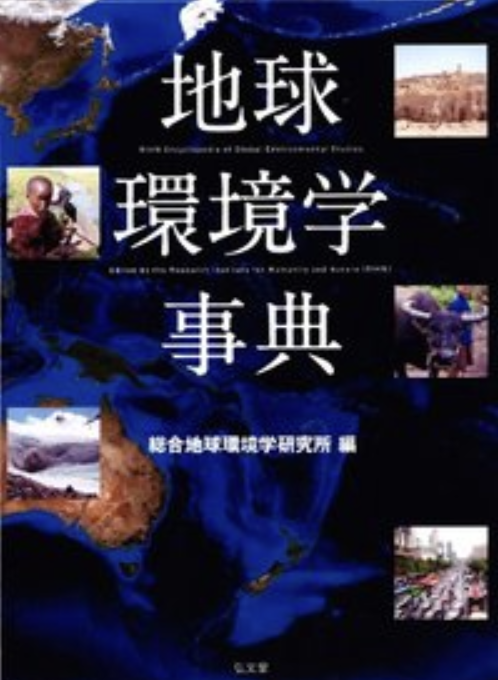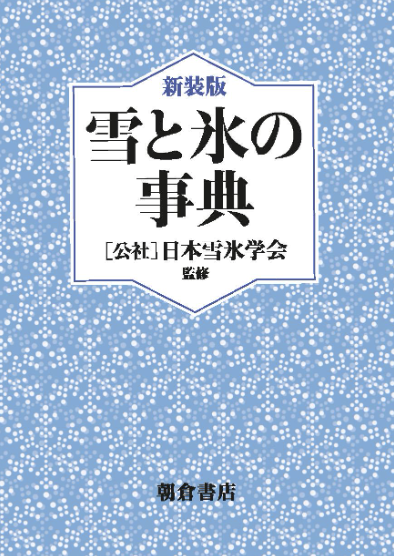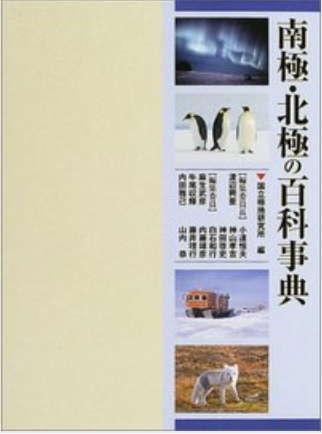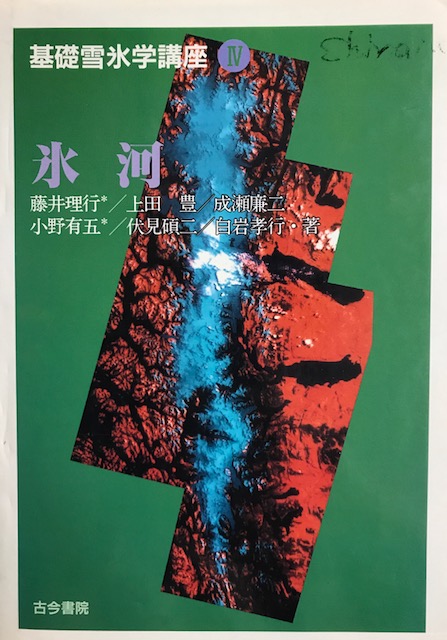TBS世界遺産というテレビ番組があります。UNESCOの世界遺産に登録された地域を紹介する番組です。ときどき、監修という形でナレーションに不正確な点がないかどうかをチェックするお手伝いをしています。以下、これまでに関わらせていただいたプログラムを列記します。いずれも氷河や寒冷地の自然をダイナミックな映像で紹介する素晴らしい内容でした。もともと空撮映像が得意な番組でしたが、最近ではUAVを駆使した斬新な映像も登場します。
研究視点で見てもいろいろ勉強になる番組です。自分では考えなかったようなアングルから氷河や地形を見せてもらうと、新しいアイデアが浮かんでくることもありました。最近放映されたモンテネグロのコトル湾の番組をみて、地中海地域の氷河作用について勉強する機会を持つことができました。
自然の仕組みをどのように視聴者に伝えるかについても勉強させてもらえます。研究者は往々にして細かい説明を長々とやりますが、核心を突いた短いメッセージやCGで事の本質をどう伝えるか、この番組はいつも考えさせてくれます。
世界遺産は年々増えているので、今後も世界の各地から素晴らしい映像を届けてくれることを期待しています。
#618 ヴェガ群島(2021/10/31)
#612 スイス・アルプス ユングフラウ-アレッチ(2021/9/19)
#606 イルリサット・アイスフィヨルド(2021/7/18)
#586 ウッドバッファロー国立公園(2021/2/21)
#576 ハイコーストとクヴァルケン群島(2020/11/22)
#563 西ノルウェーのフィヨルド群(2020/8/16)
#561 バイカル湖(2020/7/26)
#556 テ・ワヒポウナム(2020/6/14)
#524 レーティシュ鉄道(2019/9/22)
#518 アラスカ・カナダの氷河地帯(2019/8/4)
#489 ウォータートングレーシャー国際平和自然公園 (2018/12/2)
#484 グロスモーン国立公園(2018/10/21)
#481 ピレネー山脈ペルデュ山(2018/9/30)
#476 ワスカラン国立公園(2018/8/19)
#434 イルリサット・アイスフィヨルド(2017/9/10)
#404 スイス・アルプス ユングフラウ-アレッチ(2017/1/8)
#333 テ・ワヒポウナム(2015/5/24)
#309 サーミ人地域(2014/11/9)
#304 西ノルウェーのフィヨルド群(2014/9/28)
#224 アラスカ・カナダの氷河地帯II(2012.11.25)
#223 アラスカ・カナダの氷河地帯I(2012.11.18)
#190 ハイコーストとクヴァルケン群島(2012/2/26)
#172 ユングフラウ・アレッチュ氷河(2011/10/16)
#123 ワスカラン国立公園(2010/9/26)
#118 イルリサット−アイスフィヨルド(2010/8/22)
#107 テ・ワヒポウナム(2010/5/30)
SP 深津絵里と行く極北グリーンランド(2010/5/29)
#93 カナディアンロッキー山脈自然公園群(2010/2/14)
#82 西ノルウェーのフィヨルド群(2009/11/15)
#43 ロス・グラシアレス(2009/2/1)
第568回 世界遺産が語る地球46億年II 氷河(2007/11/11)
第488回 アラスカ・カナダ国境の山岳公園II(2006/3/26)
第487回 アラスカ・カナダ国境の山岳公園I(2006/3/19)