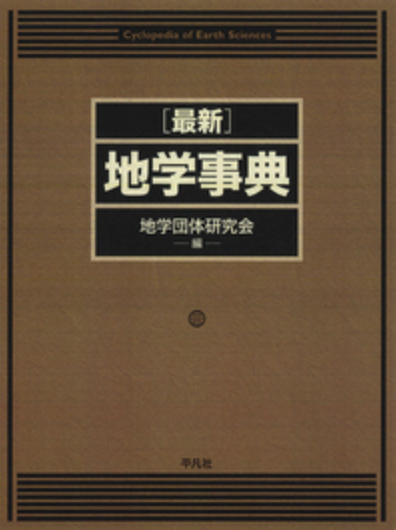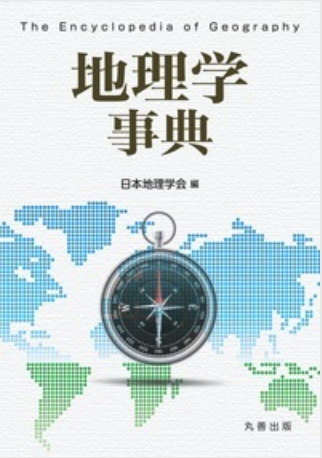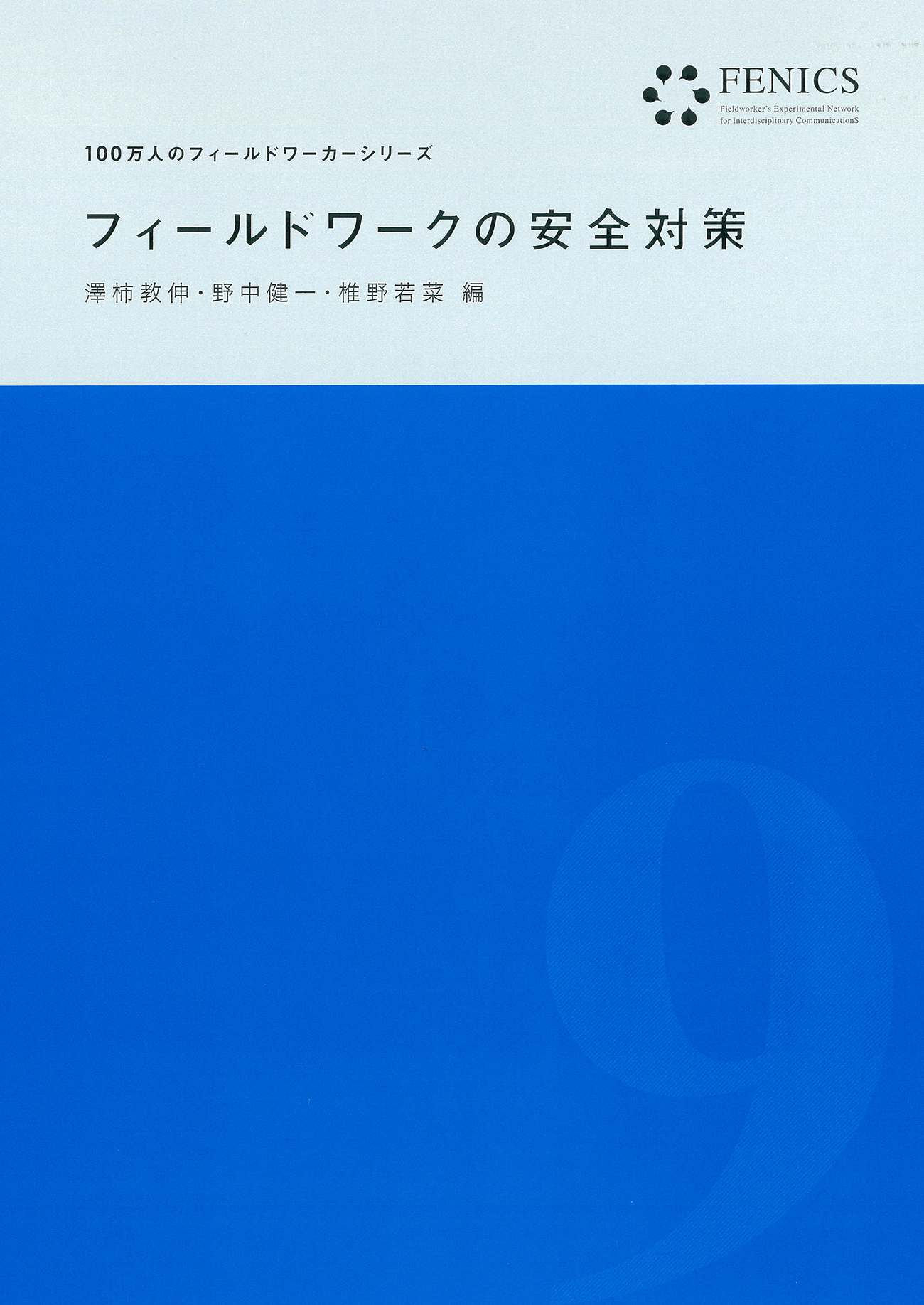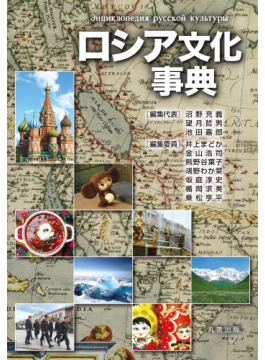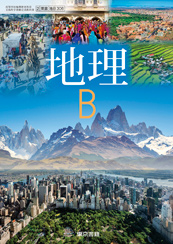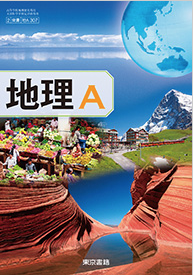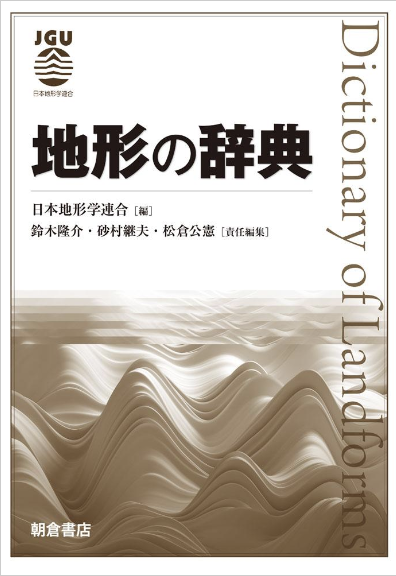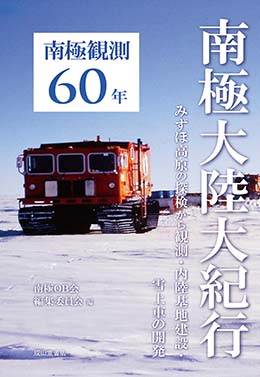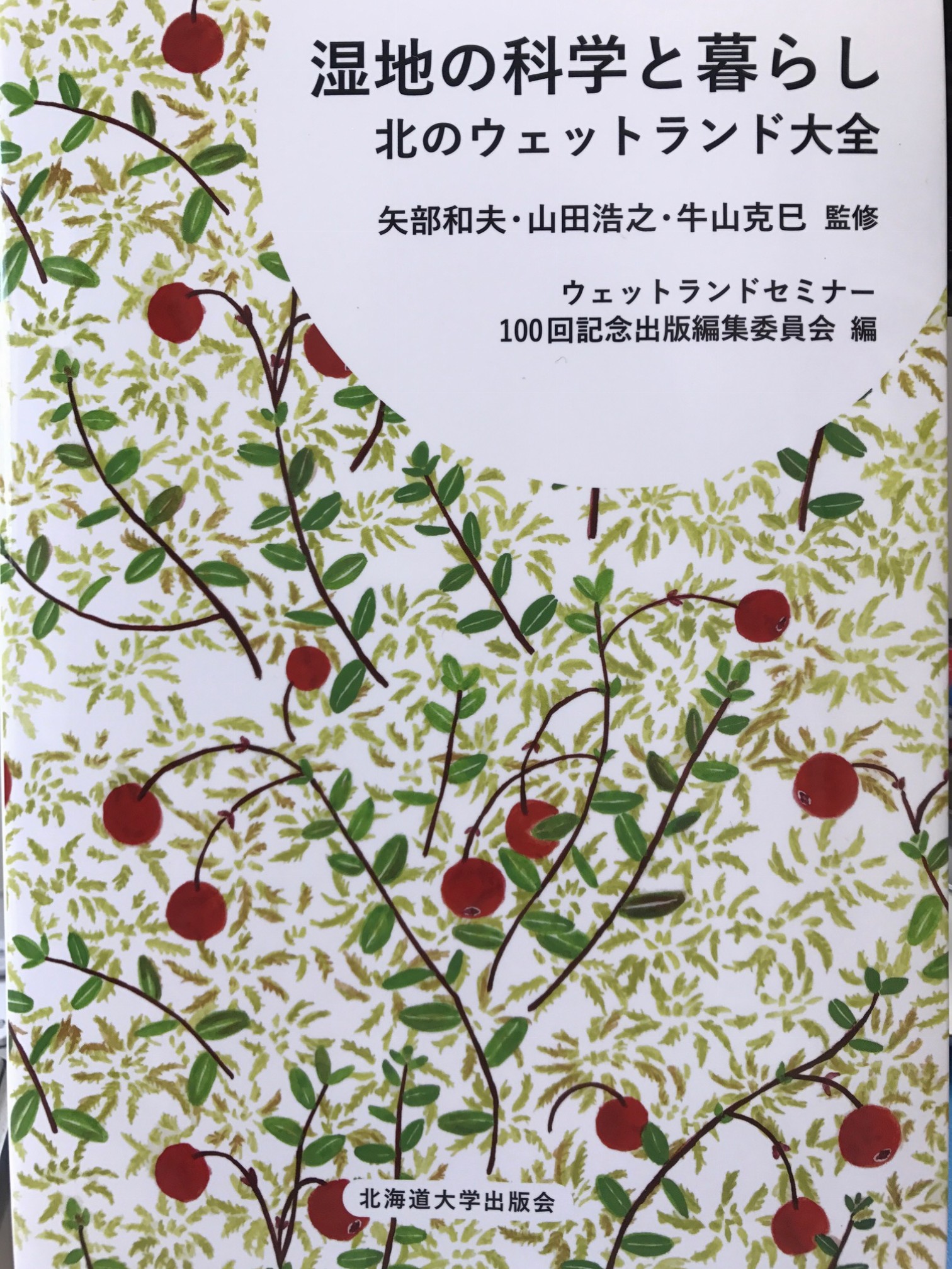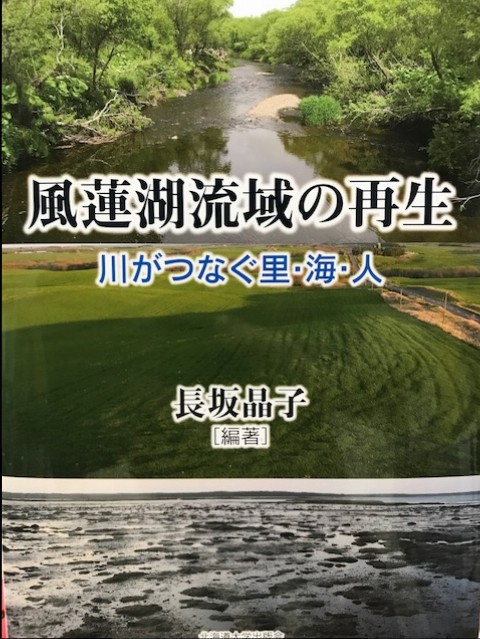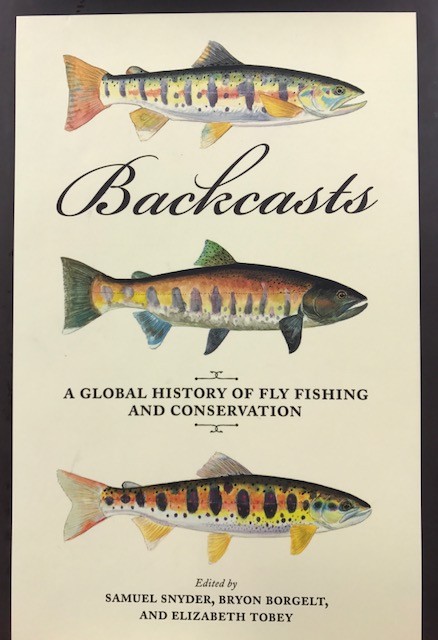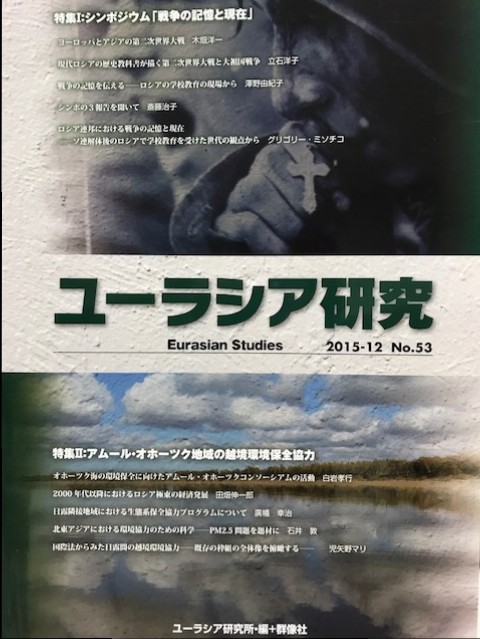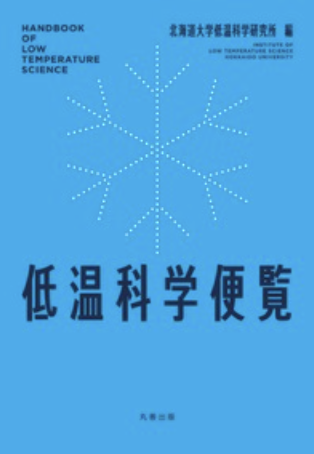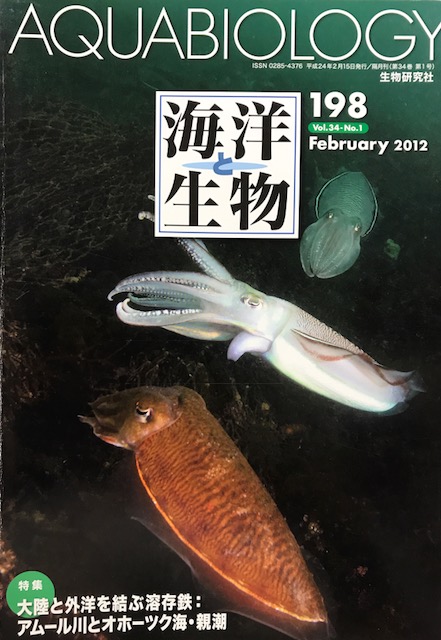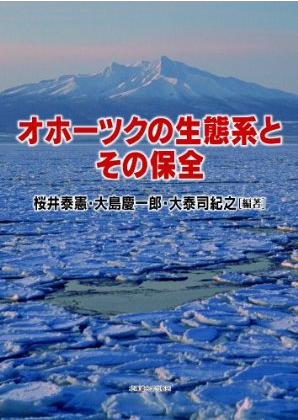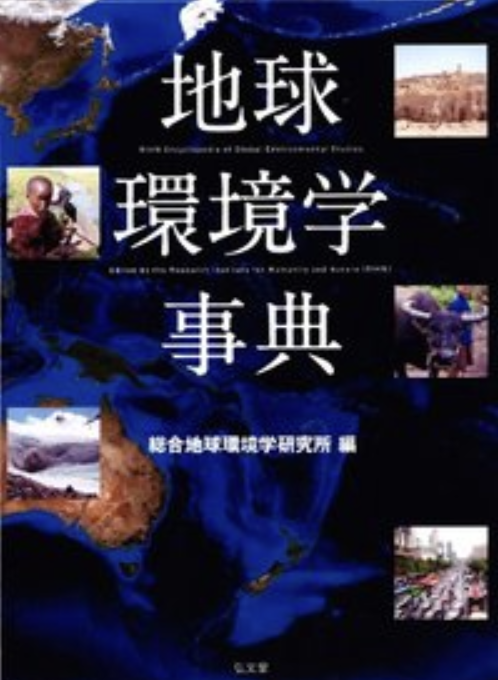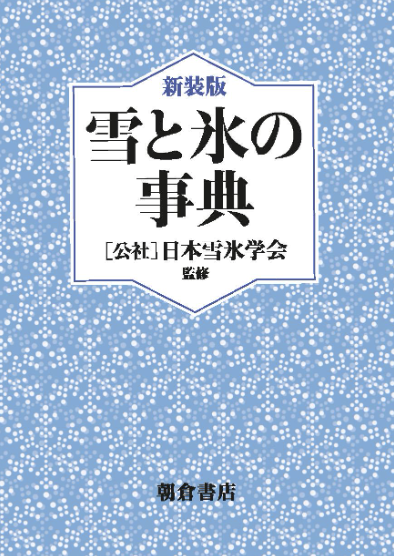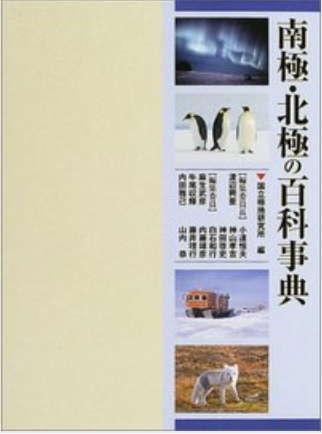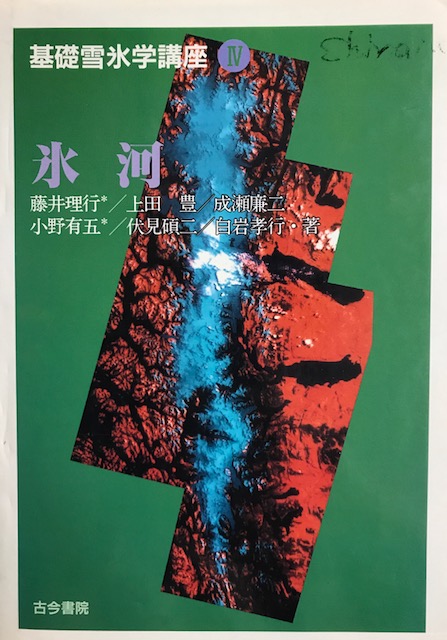長尾誠也・白岩孝行・西岡 純 (2025) 陸域結合システム:沿岸域の生物生産特性を制御する陸域と沿岸域の水塊流動と物質動態 -北海道東部の別寒辺牛川・厚岸湖・厚岸湾内外での陸海結合解明研究-.沿岸海洋研究, 63(1), 77-80. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.006
竹内祥太・雫田まき・中田聡史・伊佐田智規・白岩孝行 (2025) 北海道東部 別寒辺牛川流域における有色溶存有機物の空間分布と流出.沿岸海洋研究, 63(1), 81-89. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.007
加藤寛己・今井望百花・中川こずえ・平元正磨・西岡 純・白岩孝行・長尾誠也・山下洋平・木田新一郎・伊佐田智規・芳村 毅 (2025) 北海道厚岸湖および厚岸湾の栄養塩分布と河川由来栄養塩の寄与.沿岸海洋研究, 63(1), 91-96. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.008
長尾誠也・佐々木一樹・入野智久・伊佐田智規・白岩孝行・落合伸也 (2025) 210Pbを用いた厚岸湖・厚岸湾における陸起源粒子の移動・堆積過程の検討.沿岸海洋研究, 63(1), 103-108. https://doi.org/10.32142/engankaiyo.2025.8.010