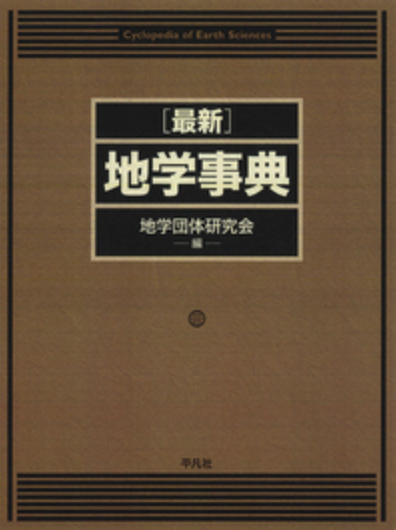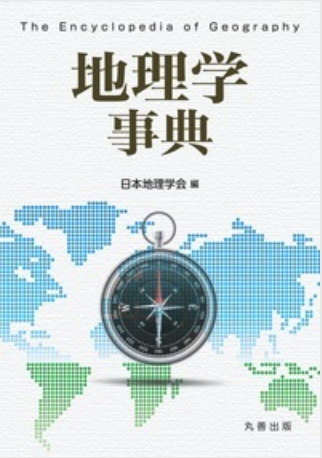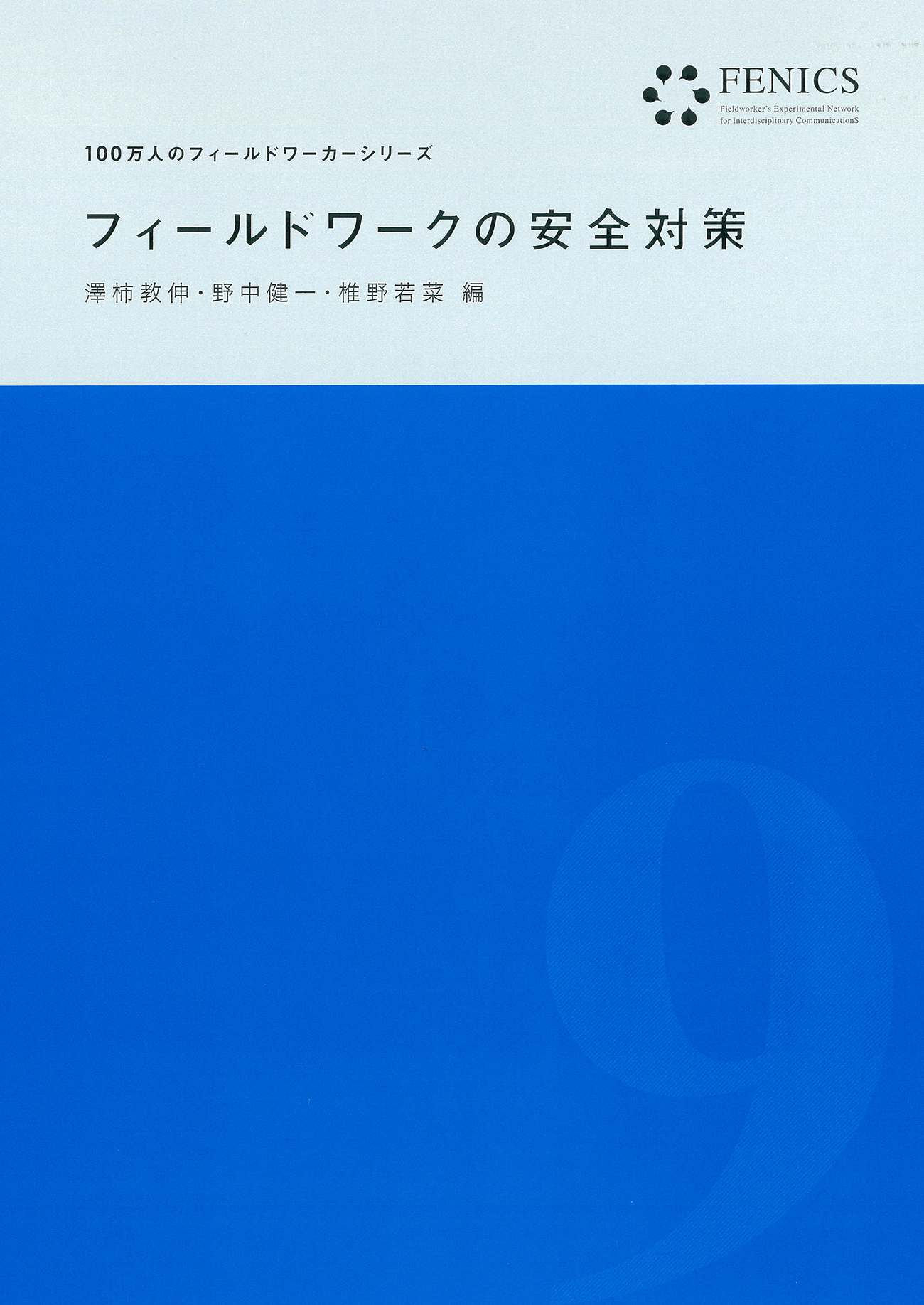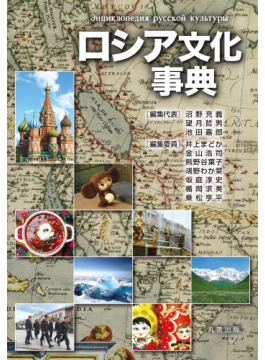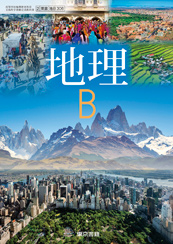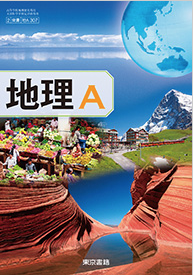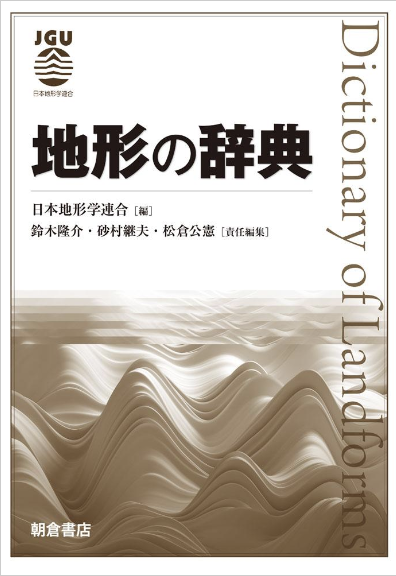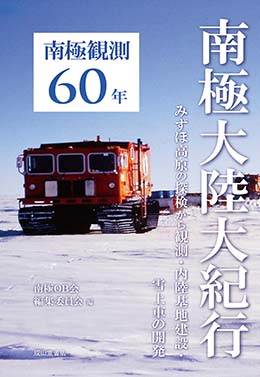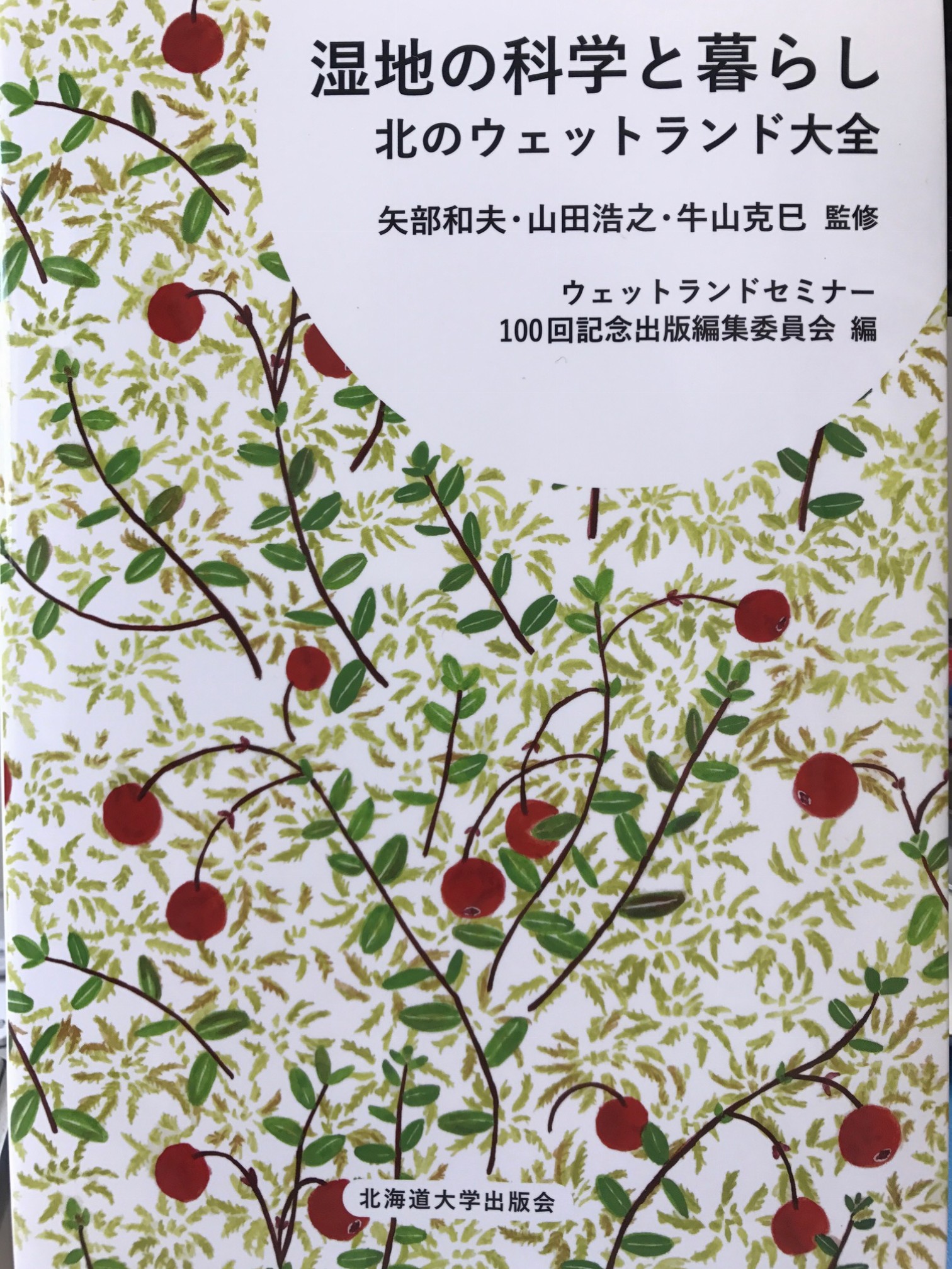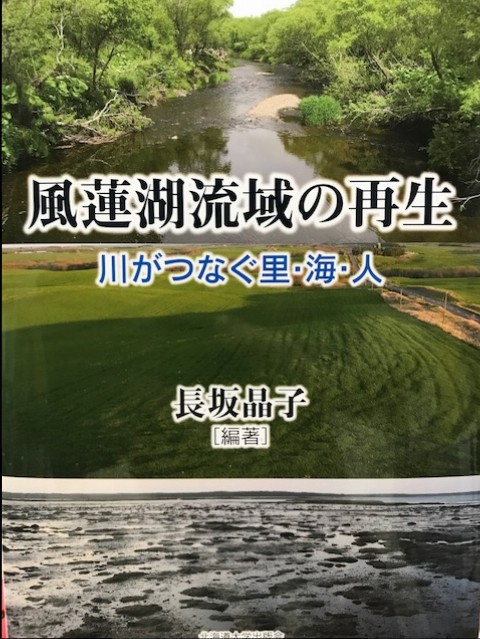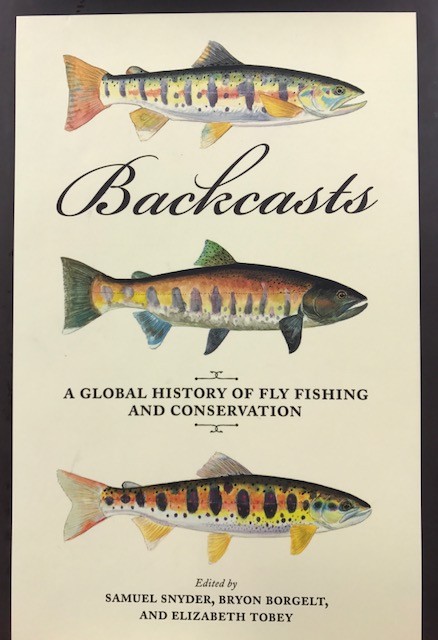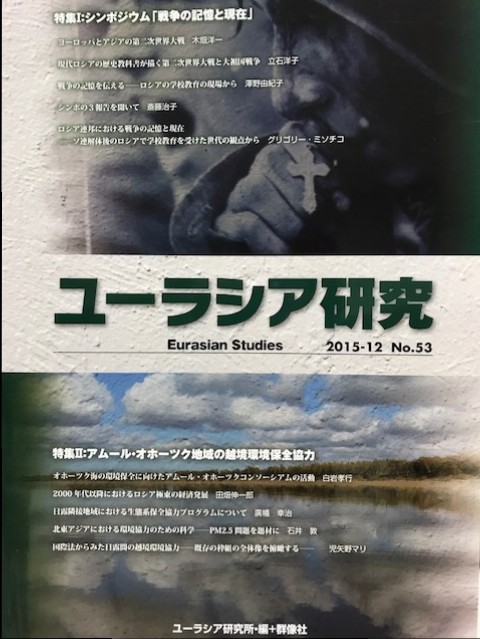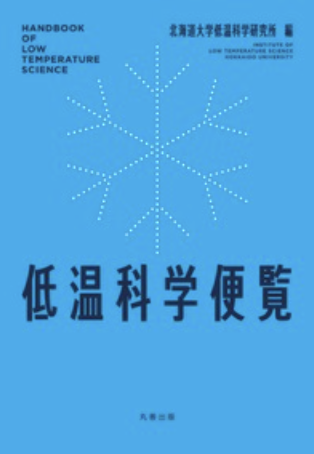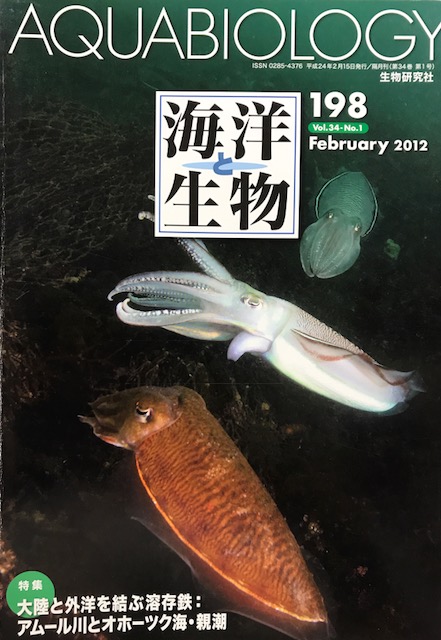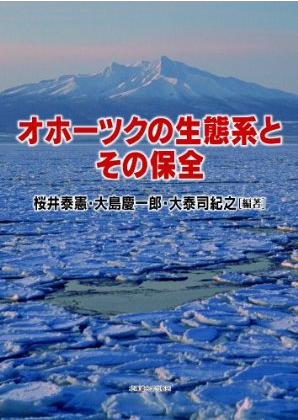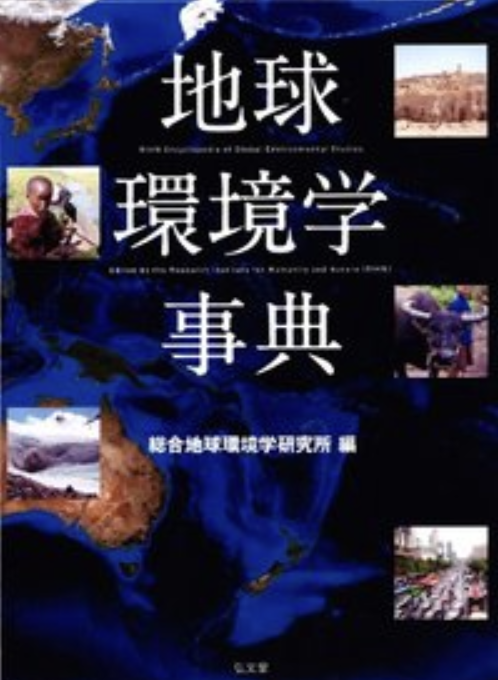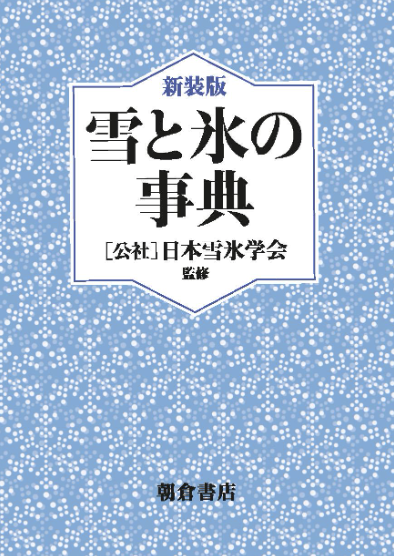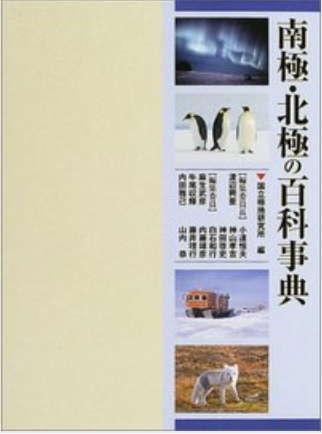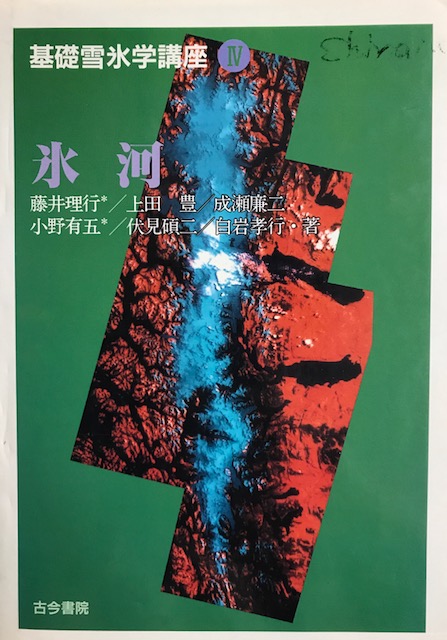10月11日から14日にかけて、2018年11月に開始した世界自然遺産知床の海岸漂着ごみ調査に出かけてきました。当研究室では、2018年〜2019年は杉田優さん、2019年〜2020年は木下拓さん、そして2020年〜2021年は西川穂波さんがそれぞれ修士論文のテーマとしてこの研究に取り組んでいます。
そもそも世界自然遺産の知床の海岸になぜ大量の漂着ごみが堆積したままになっているのかという疑問が湧いたのは、私(白岩)が知床科学委員会の委員として活動していた時のことです。同委員会の海域ワーキンググループは、さまざまなモニタリングデータを通じて、知床を取り巻く海域の環境を評価し、問題があれば改善に向けた科学的な対策を検討することを主な任務としています。海水温の変動、毎年の海氷の分布状況、クロロフィルデータによる植物プランクトン生産量の推定、海獣のセンサス、漁獲量に基づく魚類資源の動態などを評価し、知床が世界自然遺産としての基準を満たしているかについて、毎年評価を行っています。この会議の中で、海中のごみが話題になったことがあり、これに関連して海岸に漂着したごみの状況も非公式の話として出てきました。それによると、知床半島の海中や海岸部には、漁業由来の産業廃棄物や遠方から運ばれた漂着ごみが相当程度堆積しているとのことでした。
知床半島の海岸漂着ごみについては、知床財団が実施した詳細な報告書が公開されています。
知床半島海岸ゴミ回収業務報告書 平成22年3月 財団法人 知床財団
この報告書は、知床半島の海岸全域の漂着ごみの状態を地上と上空から調査し、いくつかの地点で試験的にごみを回収することによって、ごみの内容を分析し、また、堆積したごみの体積・重量を実測し、ごみの回収に必要なさまざまな課題を詳細に検討しています。また、調査によって得られた情報を、地域のステークホルダーと共有することで、海岸漂着ごみ問題の解決に向けた議論を行なっています。
しかし、このような先進的な報告書が出版されたにも関わらず、平成21年に実施された知床財団による回収実験から12年が経過した現在、知床半島の漂着ごみ問題は完全な解決を見ていません。この間、地元ボランティアと地方自治体が中心となって、知床岬周辺とルシャ地区におけるごみの回収作業を行い、知床岬周辺ではかなりの漂着ごみが回収され、ルシャ地区でも同様な状況にあります。しかし、この回収作業は一般ごみを対象とした回収であり、漁具に代表される産業廃棄物は回収の対象になっていないと聞いています。また、これらの海岸では、大量の流木がごみと混在となって堆積しており、ごみを人力に頼って効率よく回収することが難しい状況にあります。
以上のような現状を背景とし、我々の研究室では、ルシャ地区を調査対象として、海岸漂着ごみの動態調査を実施することにしました。漂着ごみがいつ、どのような状況で堆積(あるいは流出)するのか、年々の漂着ごみの質量収支はどうなっているのか、漂着ごみの内容と体積・重量の内訳などを調べています。2018年11月に調査を開始して以来、3年間のモニタリングですこしずつ漂着ごみの動態がわかってきました。この3年間、ルシャ地区の海岸漂着ごみの質量は、大きく変化しておりません。もちろん、ボランティアによる清掃活動により、一般ごみは海岸の一部で着実に減りつつあります。しかし、漂着ごみの大部分を占める漁網やロープなどの産業廃棄物は大きく変化していません。タイムラプスカメラを用いた海岸の形状モニタリングによると、初冬の高波によって、2020年12月中旬に海岸の一部が変形を受けたことがわかりましたが、漂着ごみの分布を大きく変えるほどのものではありませんでした。
漂着ごみ問題の解決が遅れている理由のひとつに、知床が世界自然遺産であるという逆説的な視点も我々は持っています。つまり、世界遺産でなければ、誰でも立ち入ることができるため、漂着ごみの存在が周知され、ボランティアをはじめとする回収作業が比較的実施しやすいという見方です。また、地域の主要な産業である漁業由来の産業廃棄物が漂着ごみの大部分を占めているという点も、地域の人々が声を上げずらい理由のひとつかもしれません。堆積している漁網やロープなどの産業廃棄物が、この地域の漁業活動に起因するという証拠を我々は持っていませんが、サケ定置網漁業に使用される土俵と呼ばれるアンカーに用いられた袋などが大量に堆積している状況を考えると、一定程度の廃棄物が地域の漁業によって出ている可能性は高いと思います。どうしたら、これらの漂着ごみを減らすことができるのか、また、いま堆積している漂着ごみを回収するには、いったいどのくらいのコストが必要なのか?世界自然遺産知床の将来を考えるにあたり、避けては通れない問題と思います。関係する全てのステークホルダーが連携して取り組まなければならない課題です。
2021年はコロナ禍により札幌市にしばしば緊急事態宣言が発出され、知床での現地調査も大きく制約を受けました。今回は、6月に続く、今年2回目の調査でした。2日間という短い時間でしたが、秋の好天に恵まれ、Phantom 4RTKを用いた対象地域の写真測量と方形区のゴミの調査を実施することができました。また、3ケ所で撮影している海岸のタイムラプスカメラのデータも取得できました。これらのデータを参考に、引き続き、漂着ごみの実態について調べていく予定です。最後になりましたが、本調査に協力してくださっている財団法人 知床財団には心より感謝申し上げます。