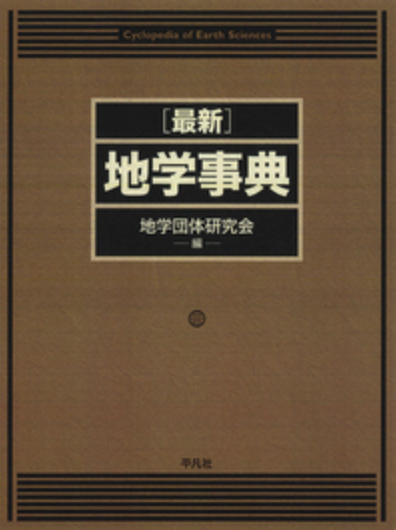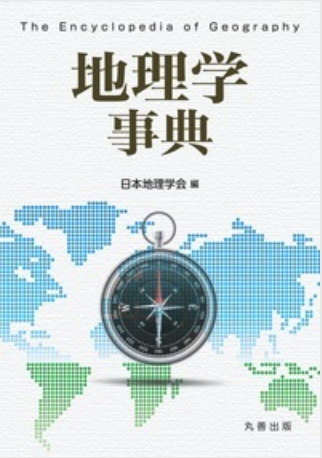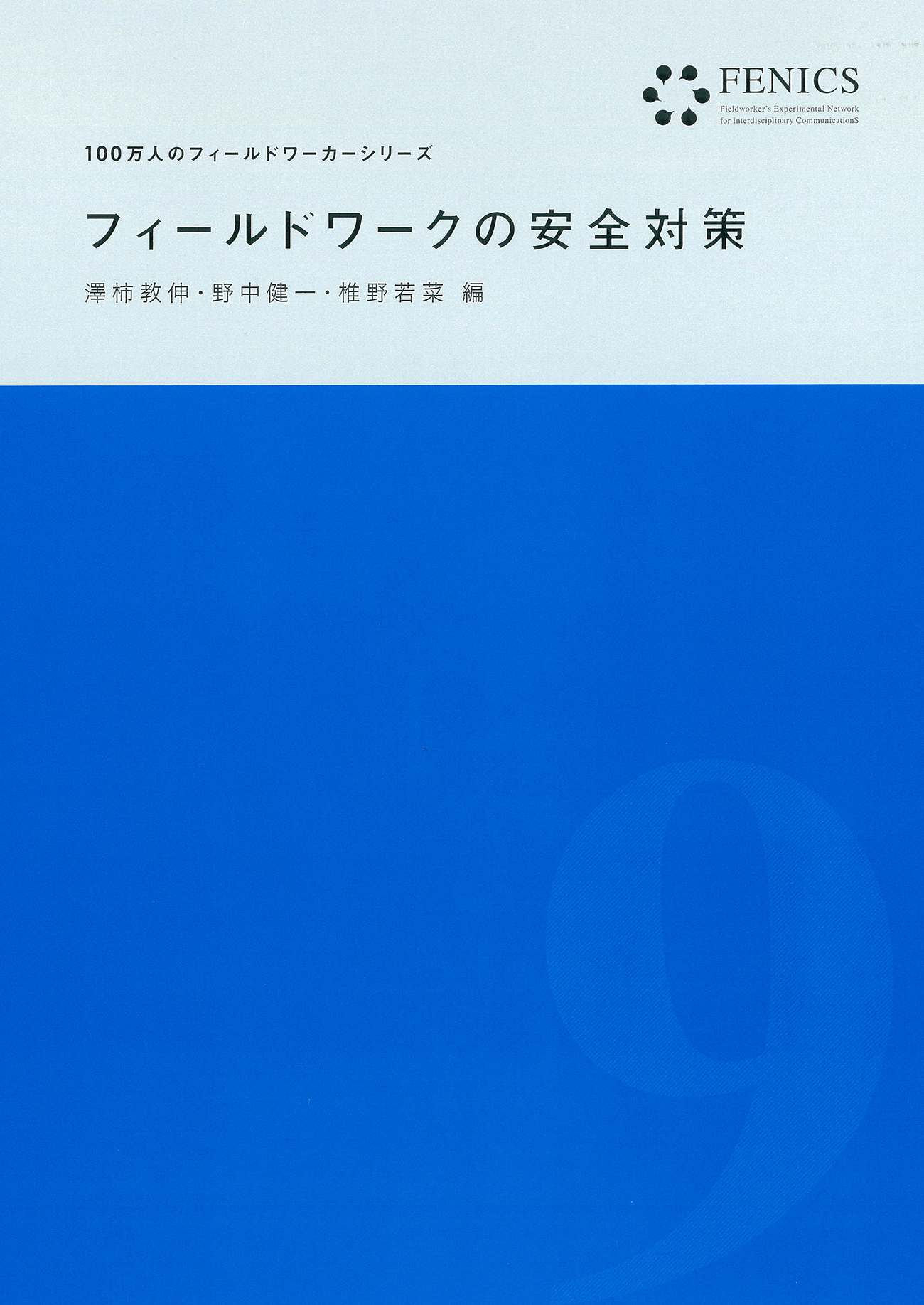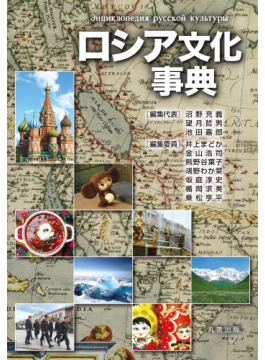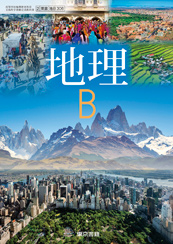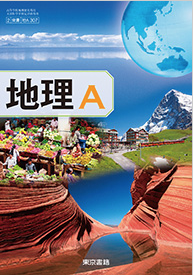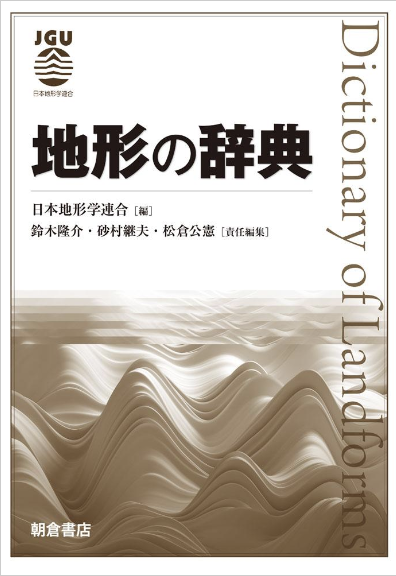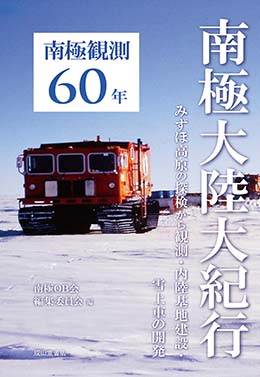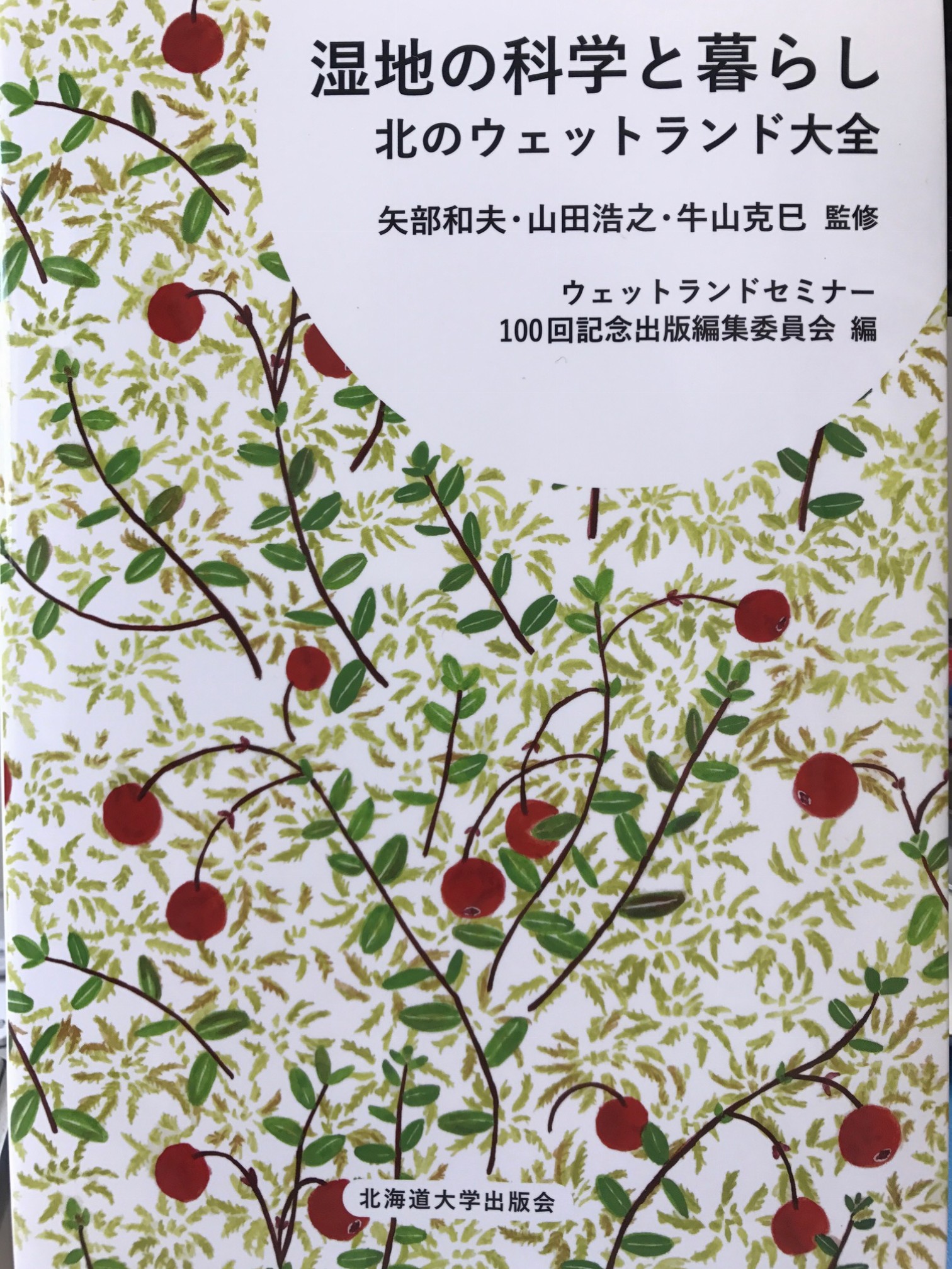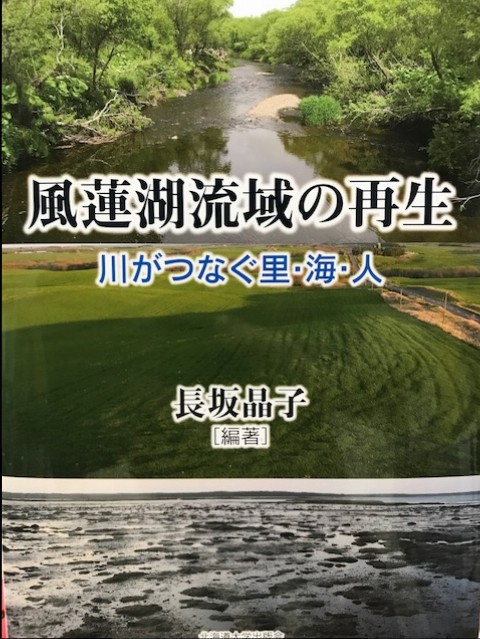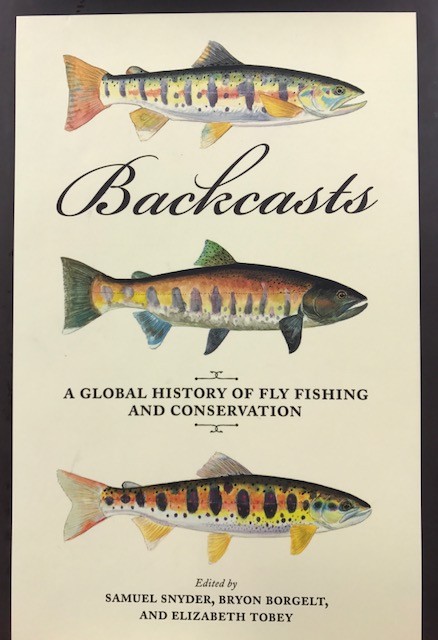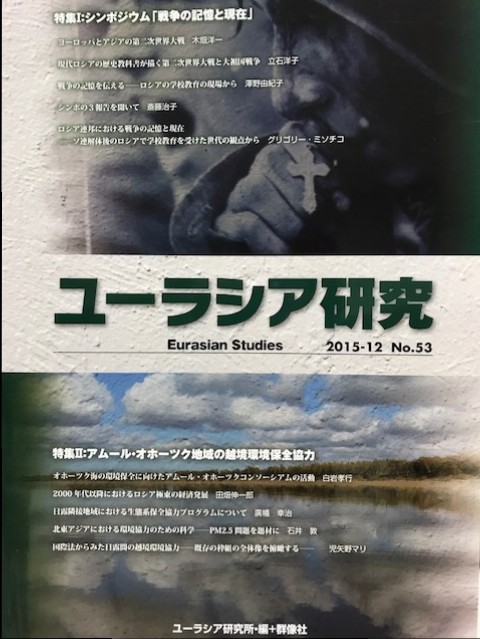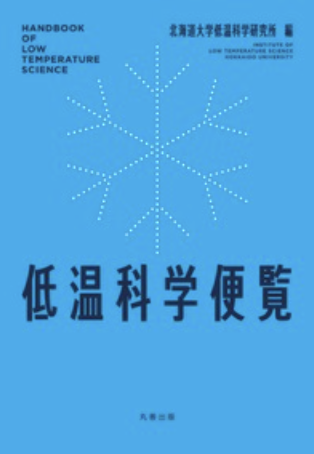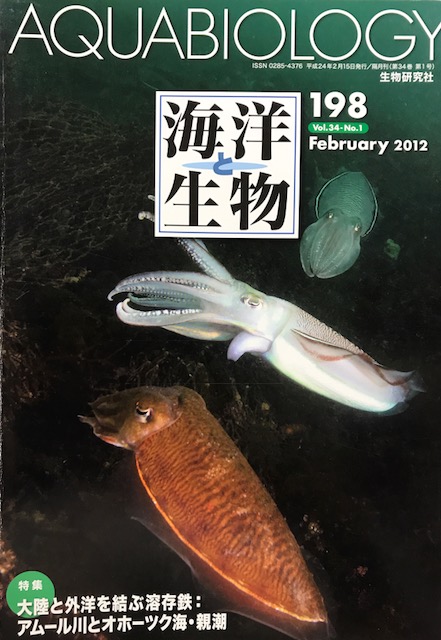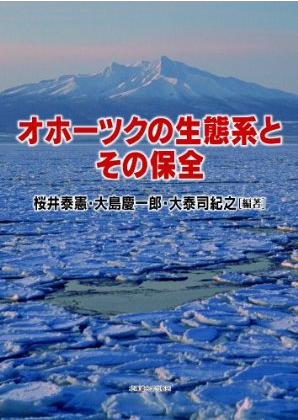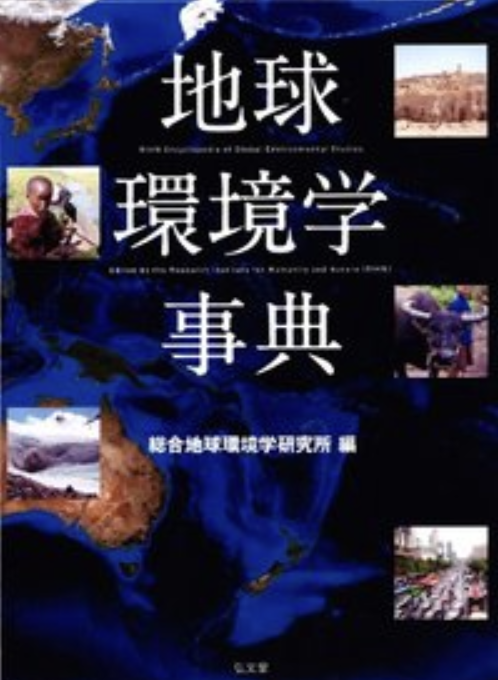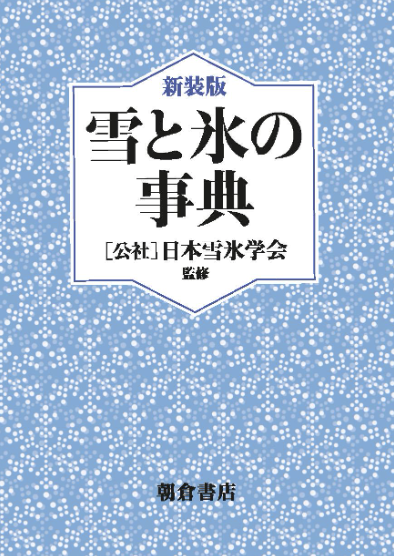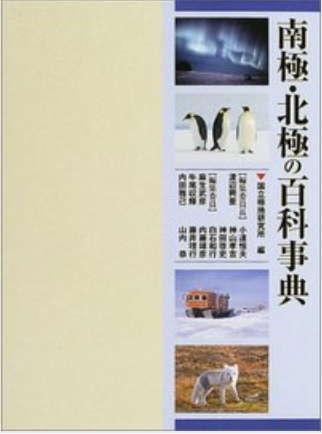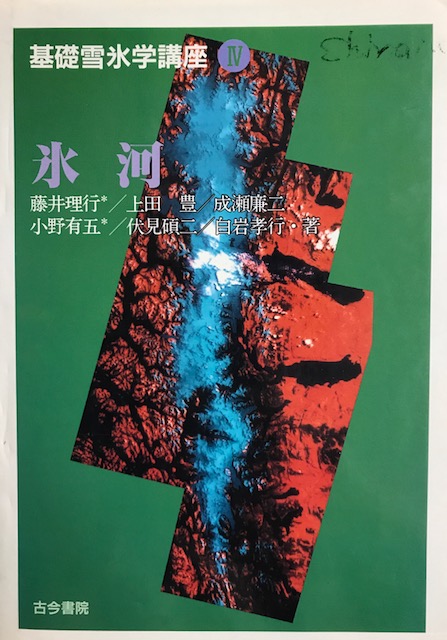2015年アムール・オホーツクコンソーシアム第四回会合に向けた国際ワークショップ
日時: 2014年12月17日(水)-12月18日(木)
場所: 北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター大会議室403
札幌市北区北9条西7丁目 Tel: 011-706-2388(直通)
会場へのアクセスはこちらのHPをご覧ください:
*参加申込不要(当日会場へお越しください)
主催:
北海道大学 低温科学研究所 環オホーツク観測研究センター
北海道大学 スラブ・ユーラシア研究センター
共催:
総合地球環境学研究所
使用言語: ロシア語・中国語・モンゴル語から日本語への逐次通訳
セッション:
セッション1 アムール・オホーツク地域の環境・持続可能な発展に関する進展
セッション2 アムール・オホーツク地域の持続可能な未来へ向けての提案
セッション3 2015年ハルビンでの国際会合へ向けて