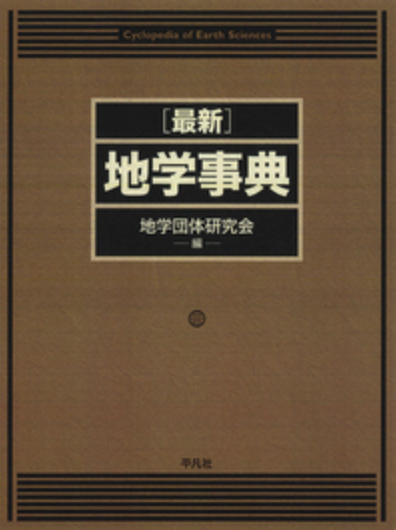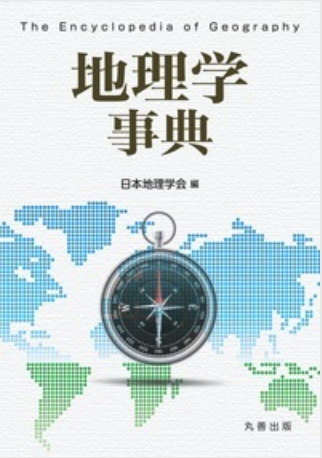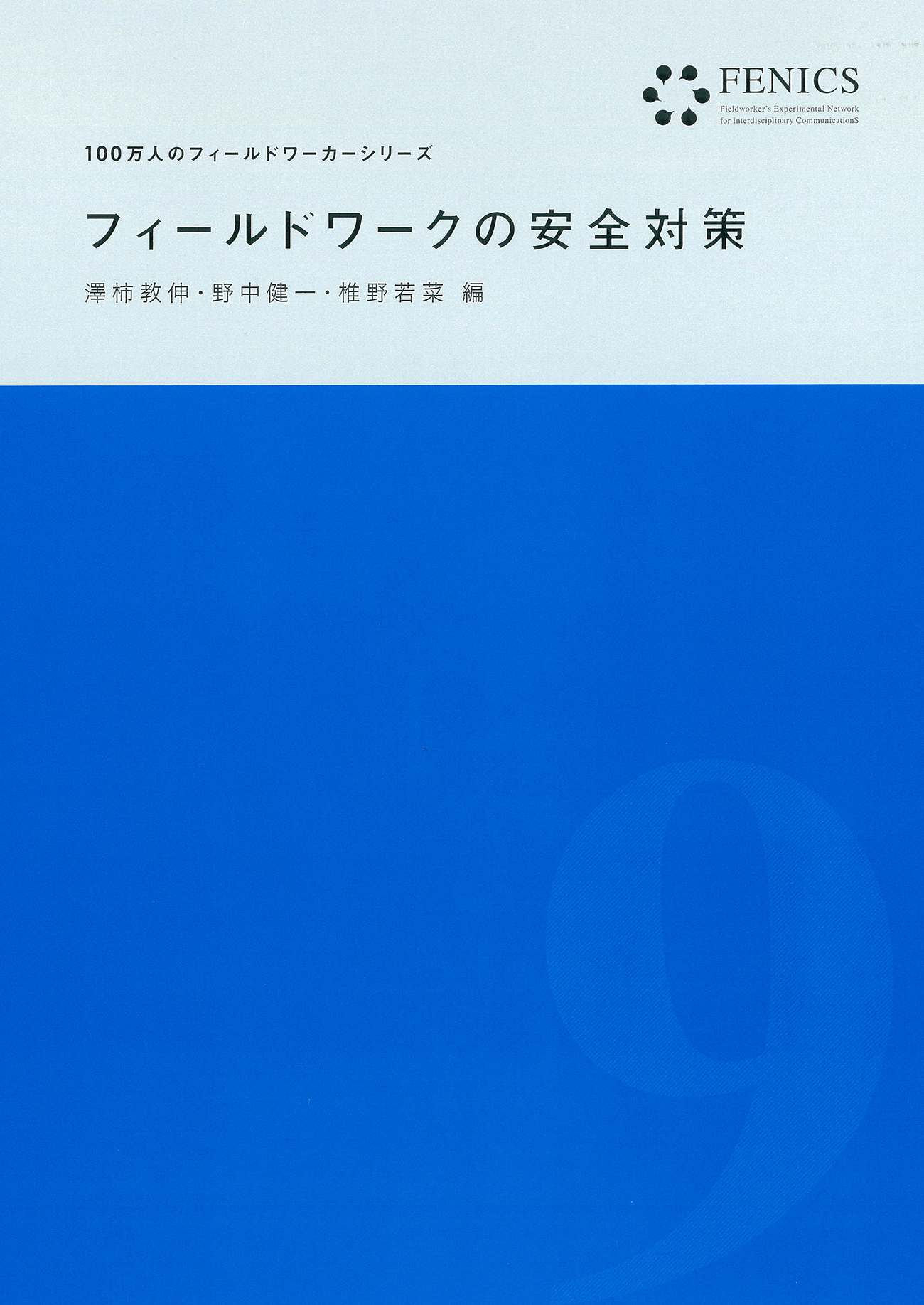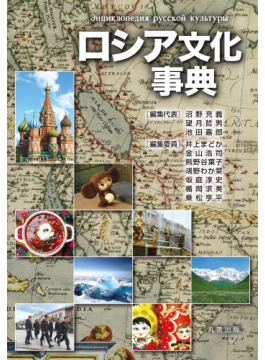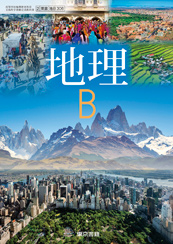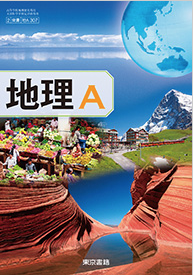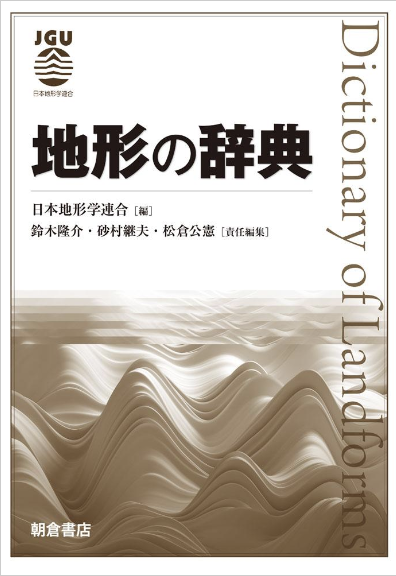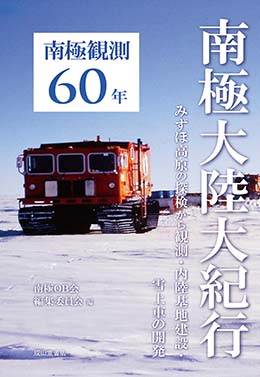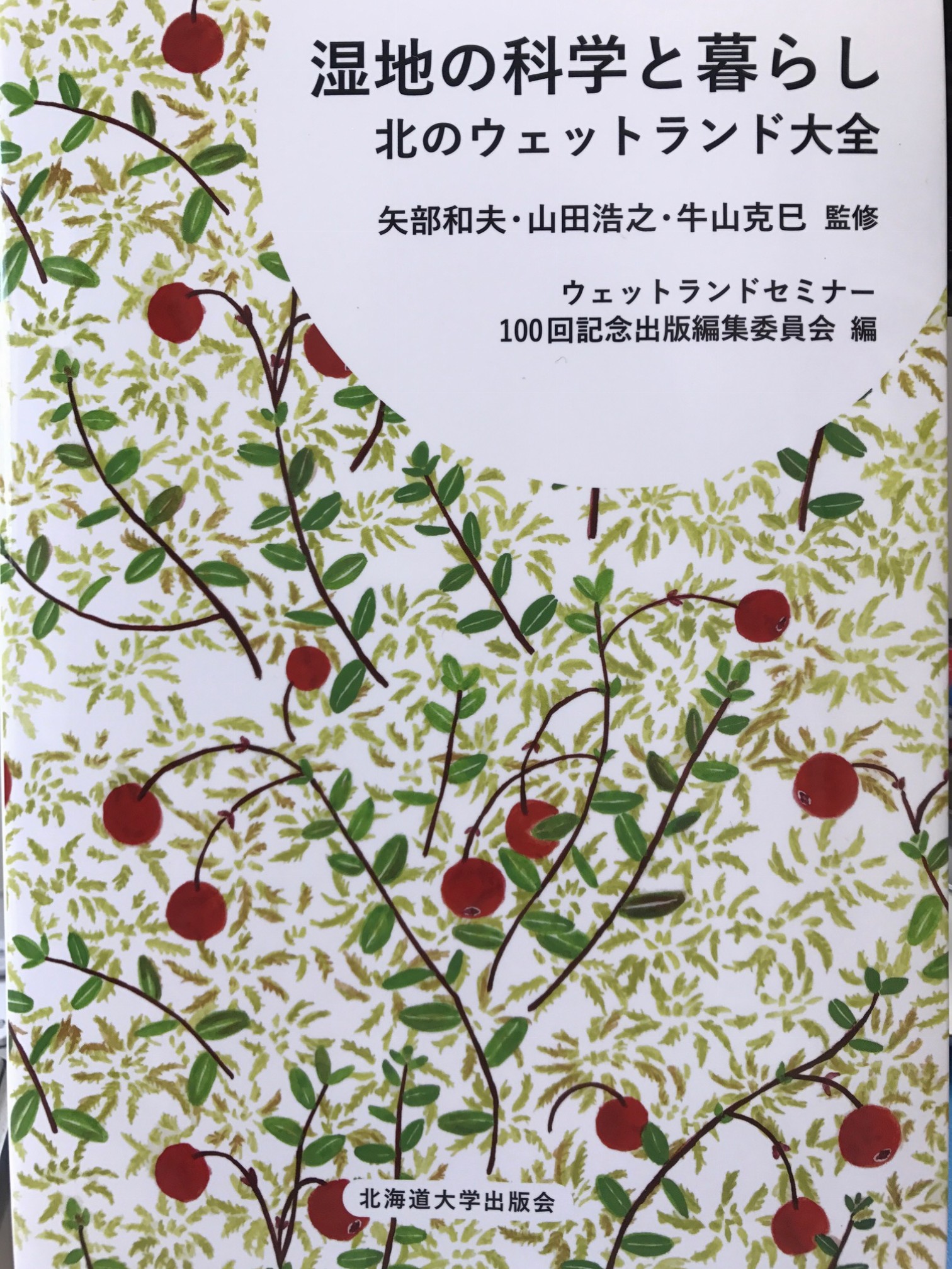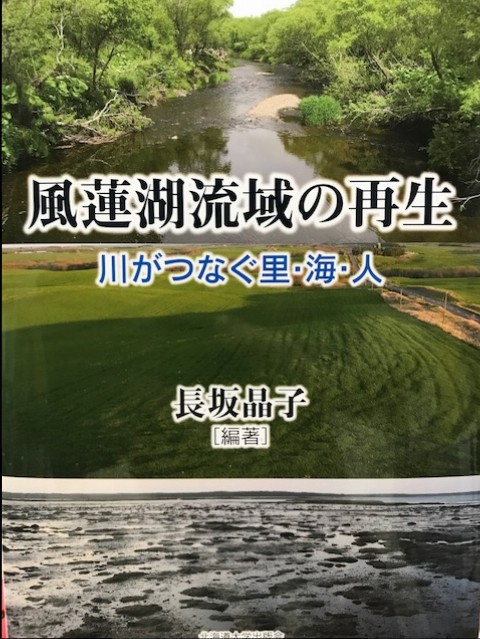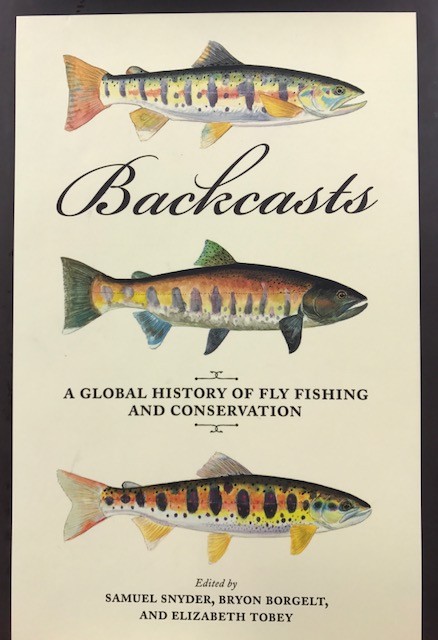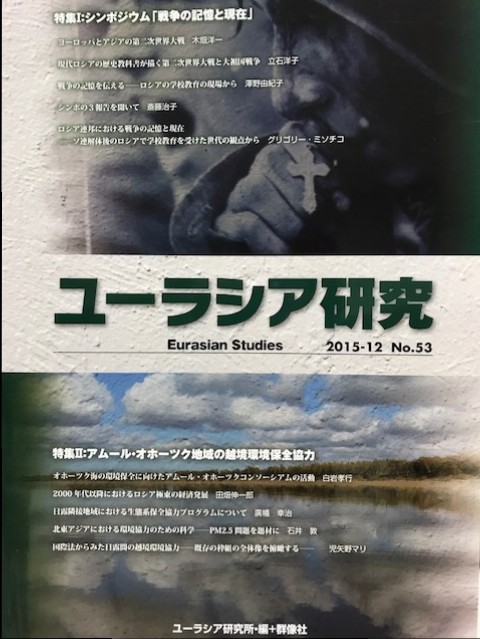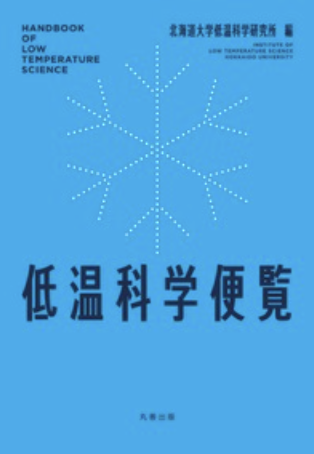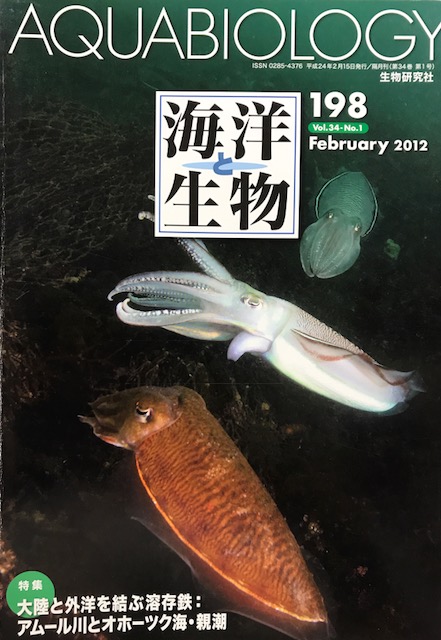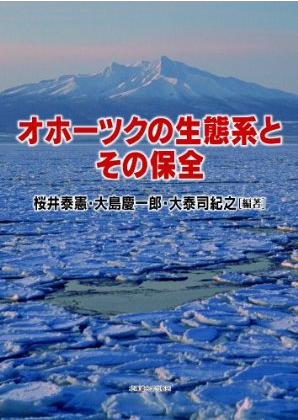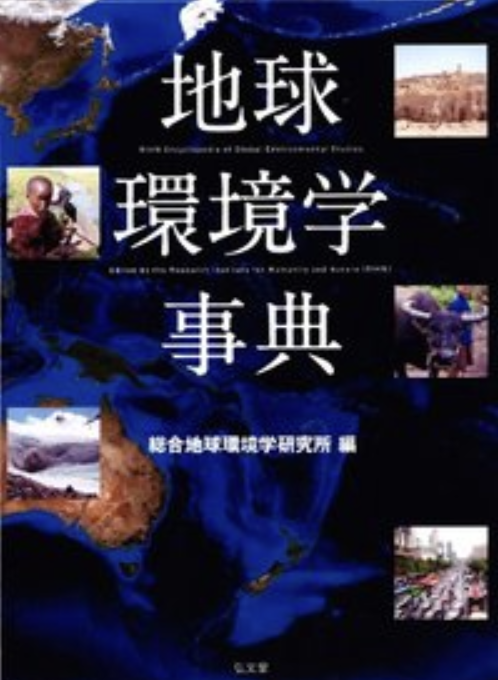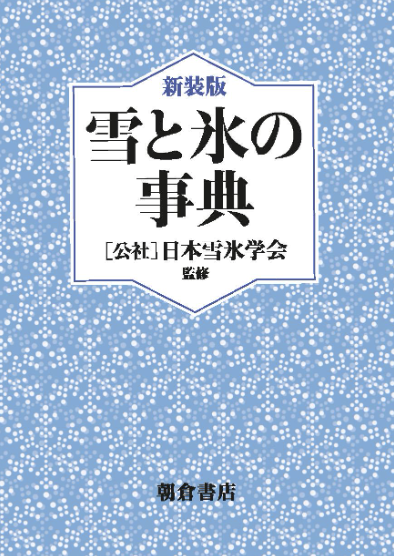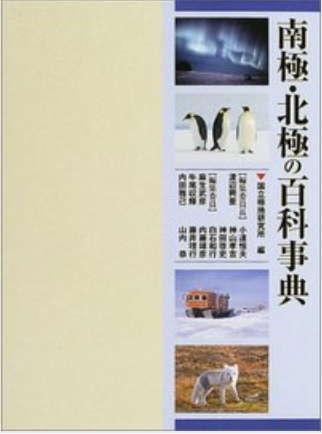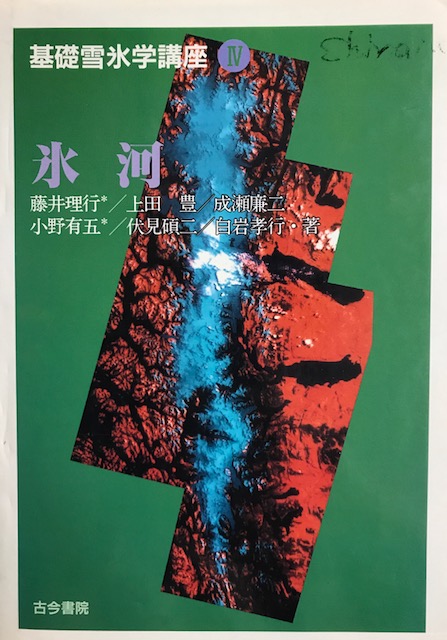コロナウィルスの蔓延で大きく混乱した2020年度が終わり、2021年度が始まりました。昨年度は、当研究室が得意としている野外調査にも制約があり、海外調査は実施できず、北海道内の調査のみ行うことができました。今年度は、新しく採択された環境省の環境研究総合推進費による課題「世界自然遺産・知床をはじめとするオホーツク海南部海域の海氷・海洋変動予測と海洋生態系への気候変動リスク評価(代表 三寺史夫)」、ベルモントフォーラムプロジェクト “Abandonment and rebound: Societal views on landscape- and land-use change and their impacts on water and soils (ABRESO) (PI: Tim White)”、科研費基盤研究(B)「表層と中層をつなぐ北太平洋オーバーターン:大陸からの淡水供給を介した陸海結合系(代表 三寺史夫)」、低温科学研究所共同利用 開拓型研究「陸海結合システム: 沿岸域の生物生産特性を制御する栄養物質のストイキオメトリー(代表 長尾誠也)」にそれぞれ共同研究者として参加し、研究室の大学院生とともに研究を進めることになりました。
研究室には、新しく2人の修士1年生を迎え、博士課程2名、修士課程4名の6名の大学院生がそれぞれのテーマで研究を進めます。上記のプロジェクトにも積極的に参加してもらい、北海道、ロシア、そしてアラスカという寒冷圏の陸面・水循環研究や海岸漂着物の研究を進めていきます。
Archive for the ‘research’ Category
当研究室で2018年から研究を開始した世界自然遺産 知床の海岸に堆積する漂着ゴミの問題がメディアで取り上げられました。まだ研究の途上ですが、遺産内の核心地域の海岸におけるゴミの現状について映像とコメントを提供させていただきました。
NHK #知るトコ、知床チャンネル 第2回「海洋ゴミと知床」
地元のボランティアのみなさんが自治体や環境省の協力を得ながら清掃活動を行っていますが、そのゴミの量は膨大で、しかも漁具などの大型ごみ(漁網やロープ)が多いため、なかなか漂着ゴミの量は減りません。また、核心地域という一般の立ち入りが厳しく制限された地域でもあるため、ボランティア活動もなかなか簡単ではないというのが現状のようです。
当研究室では、UAV(ドローン)とSfM技術を用いて漂着ゴミと流木の堆積変化をモニタリングし、漂着ゴミの質量収支を解明したいと思っております。これにより、どの時期にどれだけのゴミを回収すれば、現状の改善に繋がるのかを提言できると考えます。
2020年はコロナ禍で調査が遅れ気味ですが、9月と11月に現地調査を行う予定です。
アムール川・アムールリマン・オホーツク海のミニチュア版として、別寒辺牛川・厚岸湖・厚岸湾を選んで陸面から外洋に至る物質循環の研究が始まって丸一年が過ぎ、今年最後の観測を終えました。慣れない感潮河川の観測に四苦八苦しながらも、厚岸湾への河川流出量を定量的に把握するために、大学院生と共に2ケ月に1回のペースで厚岸を訪ねました。最後の観測は、結氷した水面を割っての観測でした。
一年を通して訪ねることではじめて見えることも多々ありました。一番印象的なのは、湿原の淡水貯留機能。どんなにたくさん雨が降っても、しっかりと湿原に貯めて、じわじわっと水を流す河川群には驚きました。感潮河川ゆえの塩水遡上と共に、川から海への物質輸送に対して大きな影響を与える機能です。
ミニチュアと言っても、それはアムール川と比べるからであって、調査をするには十分すぎるくらい壮大なフィールドです。来年は、更に詳細な過程を解明すべく、別寒辺牛川水系に通いたいと思います。

オホーツク海の熱塩循環に及ぼすカムチャツカ半島の河川からの淡水供給の影響を解明すべく、今夏はカムチャツカ半島最大の河川であるカムチャツカ川に注目して現地調査を行いました。調査を行ったのは、7月16日から7月30日の16日間。まずはカムチャツカ川の河川水が沿岸域でどのように広がっているのかを解明すべく、ペトロパブロフスクからカムチャツカ川の河口に至る沿岸海域を船舶を利用して航行しました。調査項目は水温・塩分の鉛直観測と採水です。次いで、カムチャツカ川の源流からカムチャツカ川の河口の町 ウスチカムチャツカまで陸路で移動し、カムチャツカ川の水温測定と採水を実施しました。海洋観測では船酔い、陸上観測では蚊の猛攻撃に悩まされましたが、貴重なデータを取得することができました。来年は、同様な観測をカムチャツカ半島のオホーツク海側で実施したいと思っています。
平成29年度 北海道大学低温科学研究所の開拓型研究課題(代表 長尾誠也)「陸海結合システムの解明ーマルチスケール研究と統合的理解ー」の一環として、北海道東部の別寒辺牛川水系〜厚岸湖〜厚岸湾〜沿岸親潮に至る物質輸送の研究が全国の研究者との共同研究として始まりました。
我々河川グループの研究課題は、別寒辺牛川から厚岸湖に供給される淡水量とそこに溶存している様々な物質の濃度・フラックス測定です。10月初旬の陸・汽水域・外洋の同時観測に向け、河川グループは厚岸湖に流入する河川群において流量観測と水圧式水位計・電気伝導度計の設置を行いました。

山地河川における懸濁物質(浮遊物質)の時間・空間分布観測を計画したものの、電磁流速計の故障や関係行政機関からの調査許可取得に手間取っているうちに、出遅れてしまった感がありましたが、ようやく観測を開始にこぎ着けました。4月17日に流域の積雪水量の空間分布を測定すると同時に、河床に水圧式水位計を設置し、水位の自期観測を開始しました。4月25日には流量観測を行い、水位計も再設置し直しました。近日中にADCPの設置も実施する予定です。今後は、水位変化に応じて流量観測を実施すると共に、融雪期中は2週間に一度程度、流域の積雪水量分布の観測を行う予定です。
融雪期と降雪イベントに着目し、雪が降るまで観測を継続しようと考えています。
低温科学研究所が発行している低温研ニュースに、2016年の国後島での河川調査について書きました。
Sasaki,H., Matoba, S., Shiraiwa, T. and Benson, C.S. (2016) Temporal Variation in Iron Flux Deposition onto the Northern North Pacific Reconstructed from an Ice Core Drilled at Mount Wrangell, Alaska, SOLA, 12, 287-290.