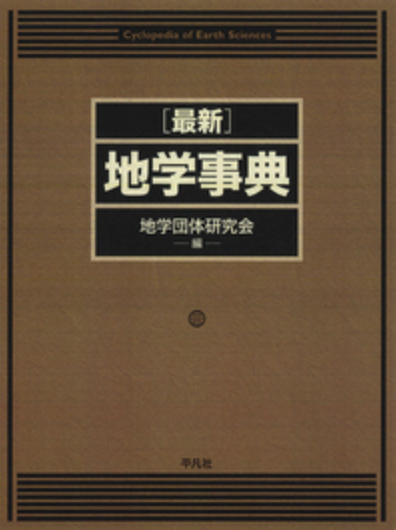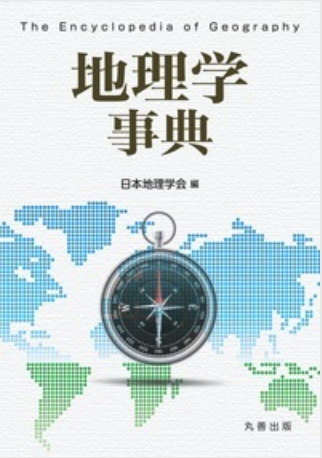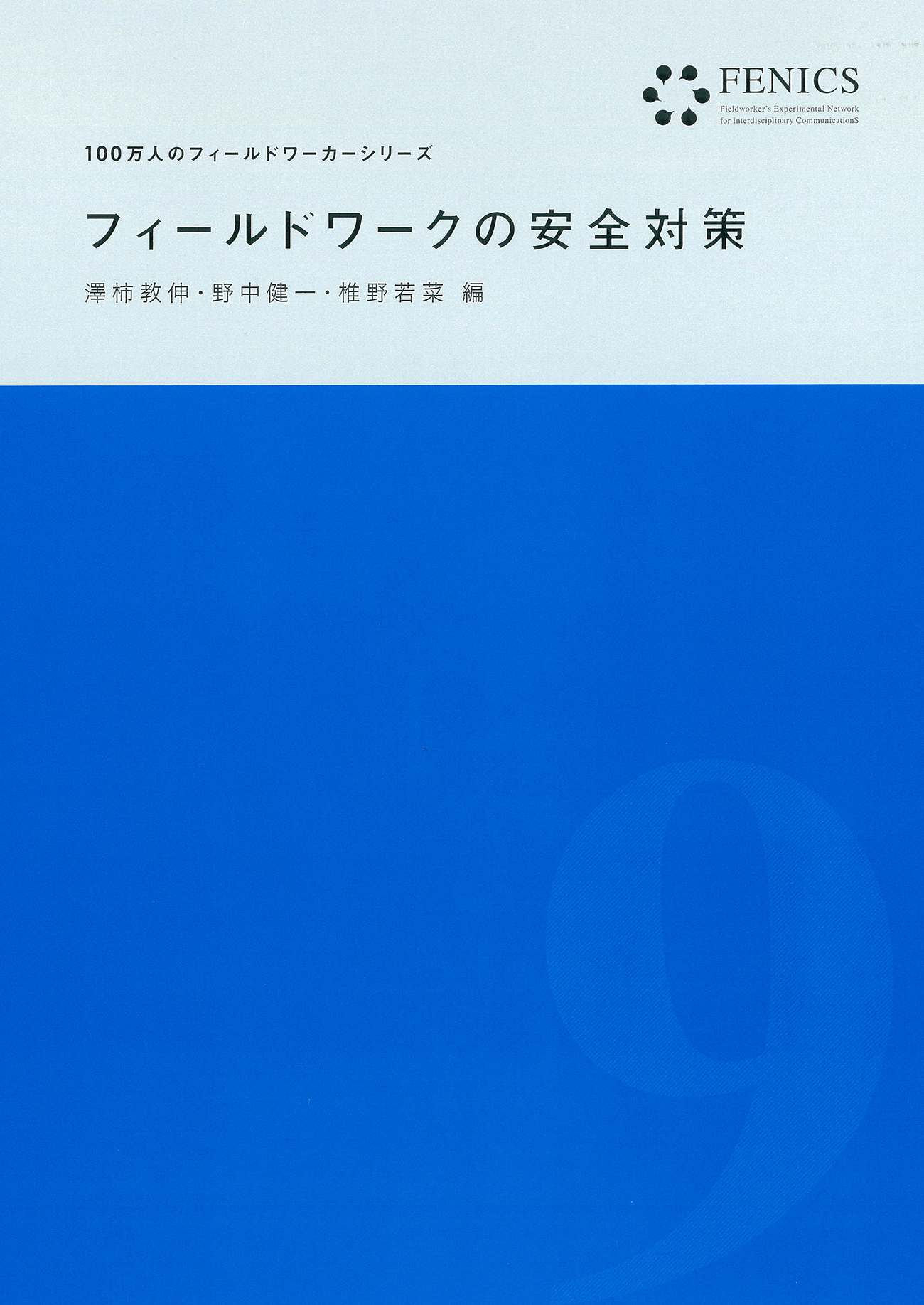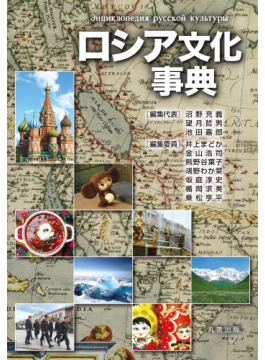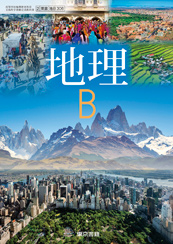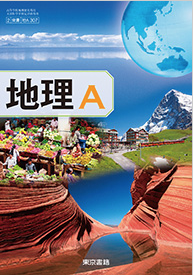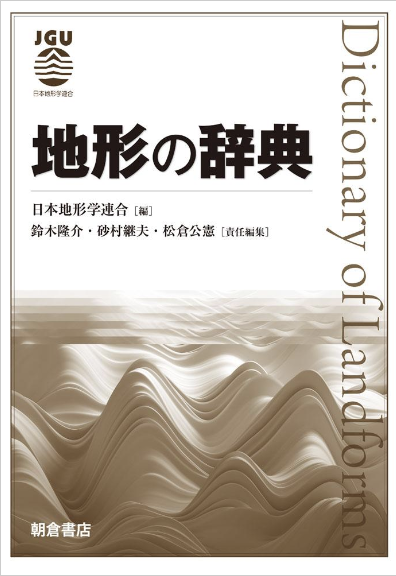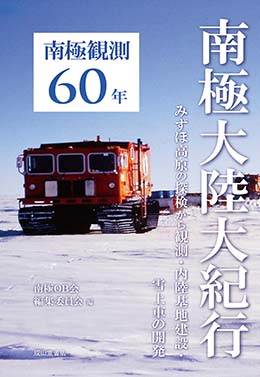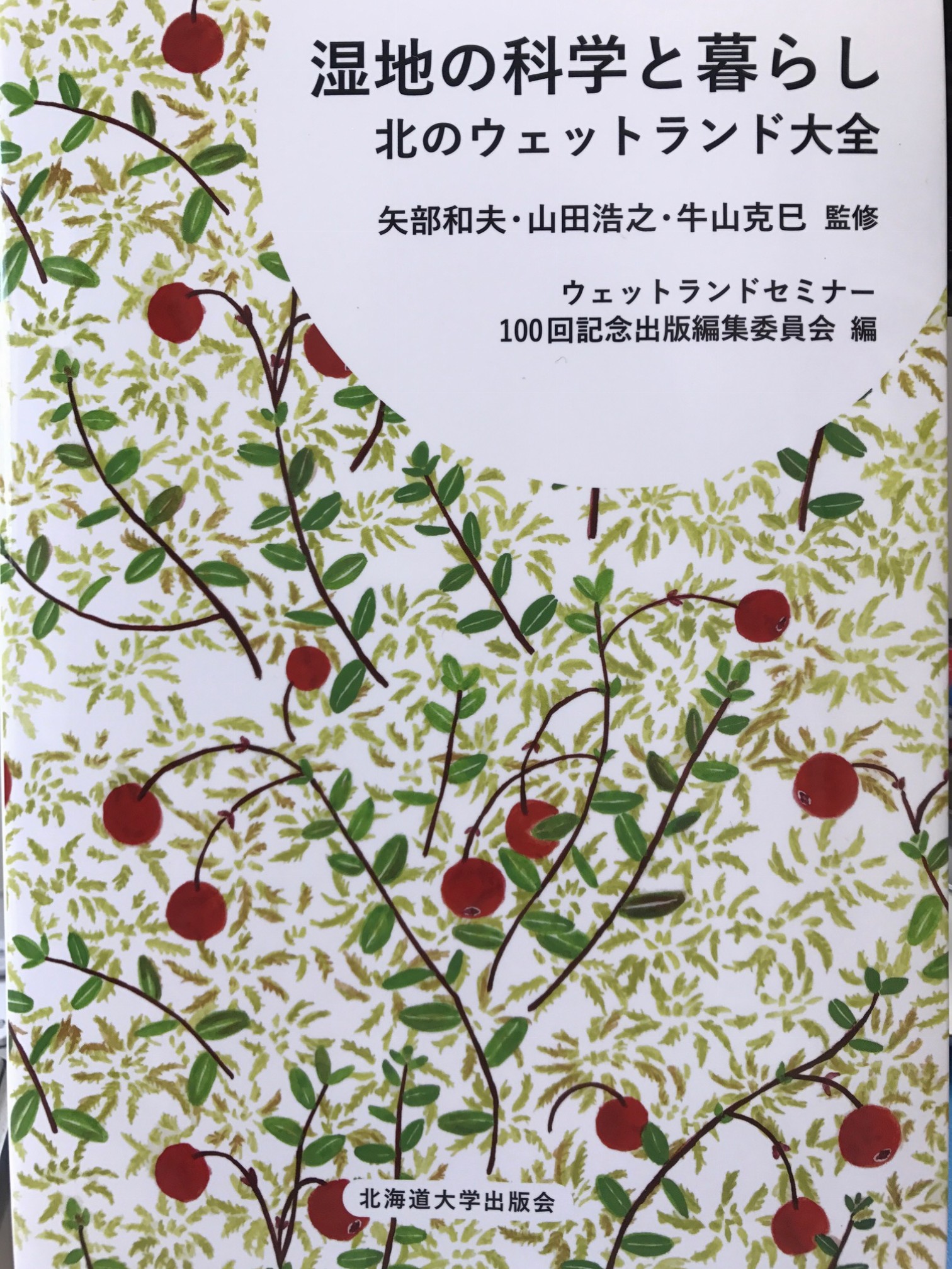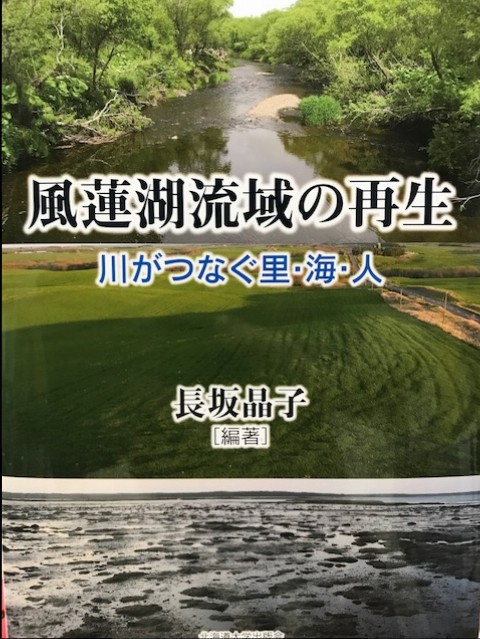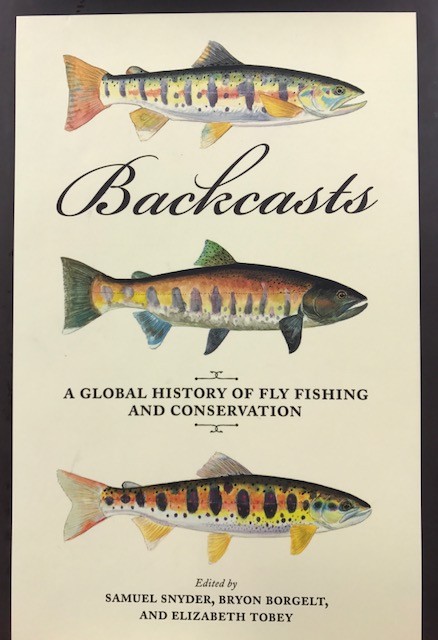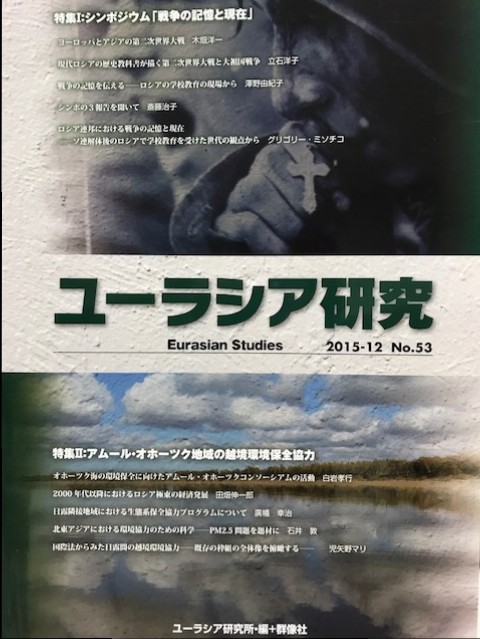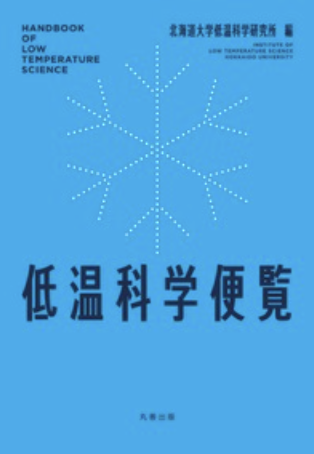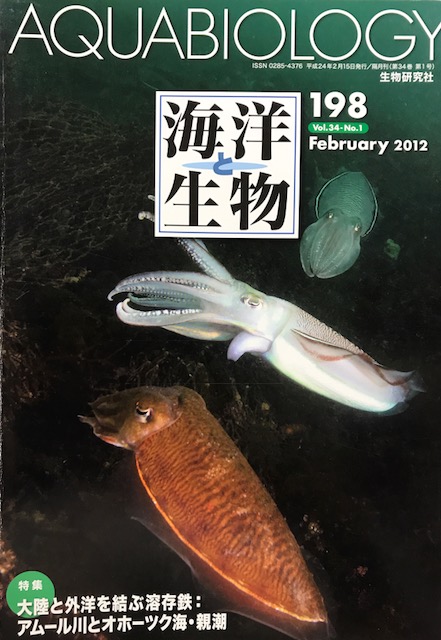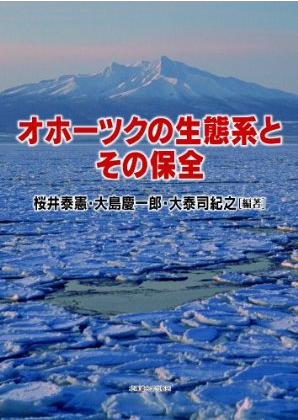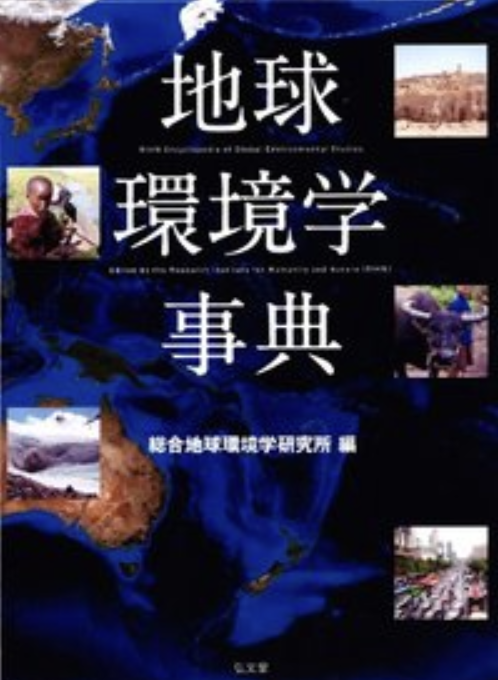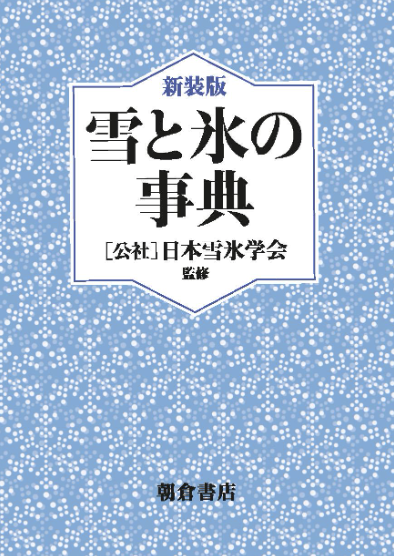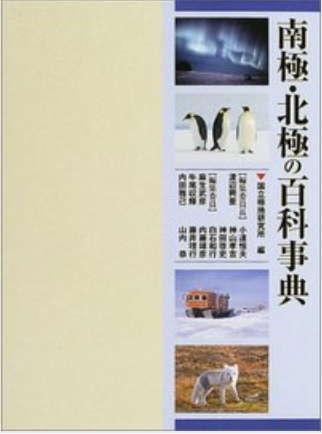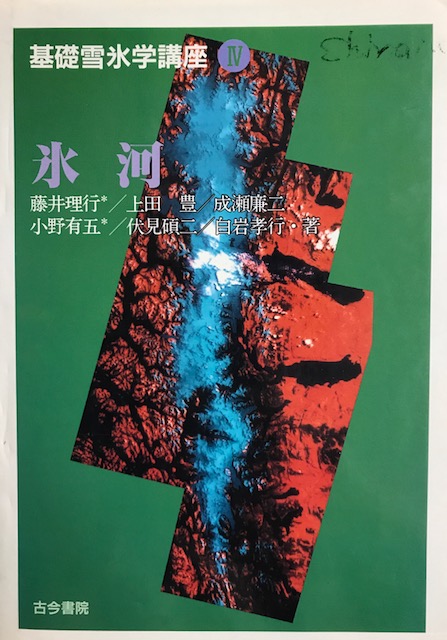白岩孝行:「鉄が結ぶ「巨大魚附林」−アムール・オホーツクシステム」、桜井泰憲・大島慶一郎・大泰司紀之編著『オホーツクの生態系とその保全』、北海道大学出版会、47-52. (2013)
白岩孝行:アムール・オホーツクコンソーシアムの設立とその意義、桜井泰憲・大島慶一郎・大泰司紀之編著『オホーツクの生態系とその保全』、北海道大学出版会、439−441. (2013)
Taniguchi. M. and T. Shiraiwa (eds.) “The Dilemma of Boundaries –Towards a New Concept of Catchment-”, Springer, 275p. (2012)
白岩孝行:「第5章 オホーツク海の命運を握るアムール川」、田畑伸一郎・江淵直人編著『環オホーツク海地域の環境と経済』、北海道大学出版会、117-138. (2012)
白岩孝行:「アムール川とオホーツク海・親潮」、向井宏監修『森と海をむすぶ川』、京都大学学術出版会、48-65. (2012)
白岩孝行:「アムールはオホーツクの恋人」、北方林学会編著『北海道の森林』、北海道新聞社、291-292. (2011)
白岩孝行:「アムール川からオホーツク海・親潮へと至る鉄の道の発見」、NHKスペシャル「日本列島」プロジェクト編著『NHKスペシャル 日本列島奇跡の大自然』、132-135. (2011)
白岩孝行:『魚附林の地球環境学-親潮・オホーツク海を育むアムール川』、昭和堂、226p. (2011)
杉山慎・白岩孝行:「第27章 氷河と氷河時代」、在田一則他編著『地球惑星科学入門』、北海道大学出版会、313-322. (2010)
白岩孝行:「氷河の変動と地域社会への影響」、総合地球環境学研究所編『地球環境学事典』、弘文堂、56-57. (2010)
白岩孝行:「魚附林 森と海をつなぐ物質循環と生命」、総合地球環境学研究所編『地球環境学事典』、弘文堂、84-85. (2010)
白岩孝行:「ベーリング氷河 世界最大の山岳氷河-」、加藤碵一他編『宇宙から見た地形 –日本と世界-』、朝倉書店、24-27. (2010)
白岩孝行:「風と水で結ばれた巨大魚付林」、総合地球環境学研究所編『地球の処方箋 環境問題の根源に迫る』、昭和堂、192-195. (2008)
白岩孝行:「第8章 氷河」、(社)日本雪氷学会監修『雪と氷の事典』、朝倉書店、277-284. (2005)
白岩孝行:「第1章 雪氷圏」、(社)日本雪氷学会監修『雪と氷の事典』、朝倉書店、4-10. (2005)
白岩孝行:「氷床下の湖」、国立極地研究所編『南極・北極の百科事典』, 丸善, 410-412. (2004)
小野有五・藤井理行・上田豊・伏見碩二・成瀬廉二・白岩孝行:『基礎雪氷学講座 IV 氷河』, 古今書院, 312p.(1997)
白岩孝行:「第10章 アルプス」、C. Embleton 編著、大矢雅彦・坂幸恭監訳『ヨーロッパの地形(上)』, 大明堂、331-384. (1997)
白岩孝行:「第14章 アペニン山脈とシシリー島」、 C. Embleton編著、大矢雅彦・坂幸恭監訳『ヨーロッパの地形(下)』, 大明堂、492-513.(1997)
白岩孝行:「キナバル」、岩田修二・小疇尚・小野有五編『世界の山々-アジア・オセアニア編』 , 古今書院、31-32.(1995)
白岩孝行:「中央チベット」、岩田修二・小疇尚・小野有五編『世界の山々-アジア・オセアニア編』, 古今書院、63-64.(1995)
秋田谷英次、成瀬廉二、白岩孝行:「第1章 阿寒の気象と積雪」、財団法人前田一歩園財団編『阿寒国立公園の自然(上巻)第1章』 ,219-262. (1993)
白岩孝行:「剣岳」、小泉武栄・清水長正編『山の自然学入門』、古今書院、99.(1992)